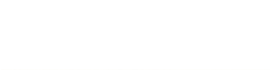
「怒りは敵と思え」
外出を自粛する生活が続いています。コロナ禍前まで当たり前のように行っていた行動がとれず、とても不自由に感じますね。自分自身に余裕がなくなると、ちょっとしたことでもイライラしてしまったり、つい一言多くなったり、何かに八つ当たりしてしまったりすることもあるのではないでしょうか。
「怒りは敵と思え」
この言葉は戦国時代の名将である徳川家康の「遺訓」(『東照公御遺訓』)として伝えられている(諸説あり)言葉の一部です。
「怒り」という感情は私たちが当然のように持ち合わせている感情です。そして、怒ることで人との関係を壊してしまう、イライラして冷静な判断を妨害してしまう、ということは私たちも分かっていることでもあります。
では、この「怒り」というものを仏教ではどのように捉えているのでしょうか。また、「怒り」という感情を無くすことはできるのでしょうか。
「怒り」は心を害する毒の一つであり、特に猛毒に値するものとされています。一切の苦しみを乗り越えることを目指す仏教において、怒りは瞬時に人の幸福を壊し、苦しみを生み出す原因となってしまいます。もちろん怒り以外にも毒はありますので、「怒り」だけを無くせば良いかというと、そういうわけではありませんが、少なくとも「怒り」を面に出すことは幸福に向かいません。
「怒り」は自我意識と大きく関わっています。たとえ自覚が無くても、どこかに「私のせいではない、私は正しい」という思いがあると、それに反することに怒りが現れます。また、物事の正否は多数決では決して決められませんが、しかし多数派の考えを持っていると、少数派の考えをなかなか理解しようとせず、「多くの人もこう思っているのだから、こっちの考えが正しい」と思いこみ、そこに賛同しないことに怒りが現れます。逆もしかり、「多くの人がそう思っても、私はそうは思わないのに理解してくれない」と怒りが現れます。
「怒り」を完全に無くすには、偏りのない、仏様の正しい智慧を持たなければなりません。つまり、「怒り」を無くすことは容易ではないのです。
お経の中には怒りのおさめ方がいろいろと説かれています。
例えば、お釈迦様の第1の弟子のサーリプッタ尊者という方は次のように仰っています。心の中に現れた「怒り」は無常であり、常に残り続けるものではない。本来は「怒り」は一瞬のものだが、自分の中で勝手に考え続けて怒りを作り続けているからおさまらない。永久に続くものではないので、怒りが表れ始めたら、その怒りの対象を考えない、見ない、聞かない。すると怒りはおさまって消えていくと仰っております。
しかし、私たちの日常では、嫌でも接しなければならないこともあります。その時は、「私が正しい」という考えがどこかに隠れていないか、冷静になって自分の考えを辿ると良いかもしれません。するとどこかに「自分がこうしたいんだ」という自我が見えてくるかもしれません。
あるいは、相手の立場に立って考えることも良いと思います。そうすると相手の考えも理解できるようになります。自我が見えたり、相手の考えが理解できれば怒りを表さずとも新たな考えに辿り着き、お互いに納得出来る結果になるかもしれませんね。
私たちは何かにつけて怒りを覚えてしまいがちです。ましてや今はイライラしやすい状況下でもあると思います。怒りをそのまま表してしまうと悪い結果になるのでしたら、怒りは自分にとってまさに敵です。次から次と生み出される「怒り」ですが、爆発させず、どんなときでも心穏やかに過ごしていけるよう、努めて参りたいものです。
合掌
法務部 佐藤