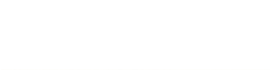「風さそう 花よりもなお 我はまた 春の名残を いかにとやせん」 浅野内匠頭長矩
法務部 竹村崇邦
元禄14年3月14日(1701年4月21日)、切腹を命ぜられた浅野内匠頭が詠んだとされる辞世の句です。
散り際が美しい桜の花は、武士の最期の姿に形容されます。その桜の花に自身をなぞらえるとともに、無念の想いが伺える歌です。
切腹の前、赤穂藩士の中でただ一人面会を許された片岡源五右衛門が、廊下を歩く浅野内匠頭と無言のアイコンタクトを交わし、最後の別れをするシーンは、「忠臣蔵」の中でも、涙を誘う名場面です。
先月末に満開を迎えた東京の桜。その後、寒の戻りがあり、最高気温が10℃を下回る日が数日あったためか、比較的に長い間、私たちを楽しませてくれました。その桜の花も、ほとんどは散ってしまいました。
桜は、つぼみがほころんだ時から、すでに散ることが定められております。きれいに咲いて、私たちを楽しませてくれた後、散るタイミングは違えども、すべて散って大地に落ちます。大地は、この花びらは美しいから受け止めるが、この花びらは汚れているから受け止めません、ということはなく、どの花びらも平等に受け止めてくれます。
私たち人間も桜と同様です。桜の花が咲いた時から散ることが定められているように、私たちもこの世に生まれた時から、すでにこの世を去ることが定められているのです。
では、私たちがこの世を去った時に、受け止めてくれる大地はどこか?
それは「極楽浄土」です。「南無阿弥陀仏」とお念仏をお称えした方には、必ず阿弥陀さまがお迎えに来てくださり、極楽浄土へと救いとってくださるのです。
この方は、極楽浄土へと救いとるが、この方は救いません、ということはございません。「南無阿弥陀仏」とお念仏を称えるすべての方を平等に救いとってくださいます。
いずれは極楽浄土へと救われる身であることを思い、お念仏を申す日暮らしを一緒に送ってまいりましょう。
合掌