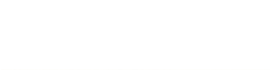
「鈍刀を磨く」 坂村真民

先日、ここ祐天寺にて少年少女精進道場が開催されました。総勢27名の子供たちが、お寺の中で寝泊まりをして、お坊さんと一緒に修行生活を体験しました。初めは、慣れないお寺での生活に戸惑うことも多い子供達でしたが、出来る限りの力で精一杯修行に励む姿が、とても立派に見えました。
仏教詩人の坂村真民さんの詩に「鈍刀を磨く」(どうとうをみがく)というものがあります。
鈍刀をいくらみがいても 無駄なことだというが 何もそんなことばに 耳を貸す必要はない
せっせと磨くのだ 刀は光らないかもしれないが 磨く本人が変わってくる
つまり刀がすまぬすまぬと 言いながら 磨く本人を光るものにしてくれるのだ
そこが甚深微妙の世界だ だからせっせと磨くのだ
※甚深微妙(じんじんみみょう):とても深く、想像できない、素晴らしい
鈍刀というのは、いくら磨いても光らないかもしれないが、せっせっと磨くことに専念し、精一杯磨いていれば、磨く本人を光るものにしてくれる。その努力をすることが大切なんだということです。
精進道場にはさまざまな子供たちがいました。親御さんと離れ、寂しくて泣いてしまう子。上手くいかず投げ出してしまう子。慣れないことも多く、頑張っても周りと同じように修行できない子供たちもたくさんいました。しかしながら、寂しくても、うまくいかなくても、出来なくても、それがその子の精一杯の姿であり、それでも頑張ろうとする姿勢が、その子を成長させてくれます。私たち大人は、周りの言葉や多くのことに影響され、鈍刀が光らないとわかると、磨くことをやめてしまいます。けれども、出来なくても何事にも精一杯取り組み、それをつづけることが、自分自身とまっすぐ向き合うこととなり、多くの気づきにつながるのだと思います。それこそが、この先のその人自身を光らせてくれます。
仏教の開祖であるお釈迦様のお弟子さんの中に、チュラパンタカというお弟子さんがいました。そのお方は、教えの言葉一つさえ満足に覚えることができませんでした。時には自分の名前も忘れてしまうほどです。それでも、お釈迦様がお教えくださった一つの教えを、ただひたすらにご修行され、ついに正しく生きていく道を見つけることができたと伝わっております。
私たちは、どれほど頑張っても鈍刀を光らせることはできないかもしれません。けれども、出来ないながらも精一杯頑張る子供たちのように、今できる精一杯の力で精進し続けること、それが何より大切なんだということを精進道場に参加した子供たちから学ぶことができました。私自身も精一杯精進を続けてまいります。
合掌
法務部 中野蓮音