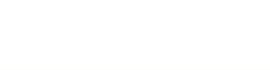

歌舞伎・浄瑠璃と仏教(十三)※正しくは十四
不動明王(その3)
祐天寺研究室 浅野祥子
不動明王は、大日如来が悪をこらしめるために憤怒相に化身したとされます。火生三昧に入って一切の罪障を破り、動揺しないため不動と言います。
左目を細く閉じ、下の歯で上唇をかむ憤怒形。辮髪を垂らし、猛火を背負って右手に利剣、左手に羂索(縄)を持って煩悩を断じる姿を基本とします。
◆貞把上人の奇瑞
増上寺の小僧だった貞把上人は、物覚えが悪く、お経を習ってもすぐ読み方を忘れてしまうのでした。これでは僧侶になることはできない、……思い悩んだ貞把上人は、開山堂に7日間のお籠もりをします。満願の日に夢のお告げで成田山にお籠もりするように告げられた貞把上人は、今度は成田山に21日間の参籠をします。その満願の日、とろとろとまどろんだ夢に、生身の不動明王が姿を現し、「長い剣と短い剣、どちらを呑むか」と言いました。鋭い剣は、どちらを呑んでも死ぬのは確実でしょう。「長い剣をください」と、思い切って言った貞把上人の喉に、不動明王は長剣をぐっと突き入れました。「あっ」と叫んで悶絶した貞把上人。やがて涼しい風が吹いてきて気が付いたときは、夕方でした。「夢だったのか…」と思いましたが、見回すとそばには長剣が落ちており、衣は喉からの血で赤く染まっていました。
それからというもの、貞把上人は一山の中に並ぶ者がないほど頭脳明晰、優れた学僧となり、のちに増上寺の第九世法主となり、生実大巌寺も開いたということです。
この貞把上人の説話は、いつしか祐天寺開山祐天上人のこととされるようになりました。祐天上人が館林善導寺の不動尊にお籠もりしたという伝説も別にありますが、祐天上人が成田山の不動尊に参籠したという話は、江戸時代には皆が知っている有名な話となったのです。今回ご紹介する歌舞伎『法懸松成田利剣』の中にも、この場面が登場します。
◆名号の利益
祐天上人に関して、江戸の人々の間でもう1つ有名な信仰がありました。それは、上人の書かれる「南無阿弥陀仏」の名号が、利益をもたらすということです。火事にあっても焼けなかったという「不焼の名号」、所持する者が7太刀斬られても怪我がなかったという「剣難七太刀の名号」など、有名な名号の話が現れました。そのため、人々は争って祐天名号を求めたのです。『法懸松成田利剣』の中にも、刀で斬られたが祐天名号を持っていたために疵を負わなかったという話があり、「剣難七太刀の名号」の話が生かされています。
『法懸松成田利剣』
四世鶴屋南北の作。文政6年(1823)6月、江戸森田座で初演されました。この作品は日蓮上人の話と祐天上人の話を両方採り入れているのですが、そのうち、祐天上人にかかわる部分をご紹介していきましょう。
芝居の中で祐天上人は、祐念上人として登場します。
無知文盲を嘆く浄土僧祐念は、日頃から信仰する不動明王の示現に遭い、「誠の智恵を得るためには明王の2振りの剣のうち1振りを呑んで悪血を出し、新血を生じさせる必要がある」と、お告げを受けます。望んで長剣を呑んだ祐念は、その場に悶絶しますが、蘇ったときには誠の智恵を得ていました。
一方石和川川端で、浪人久保田金五郎が旅の途中で没した妻の菊を葬り、通夜をしています。実は菊は、下総羽生村百姓助の妻であったのですが、金五郎と密通をしてここまで逃げてきて死んだのです。ところがそこに、女敵討ちをしようと2人を追う助が来合わせ、金五郎と知って打ち掛かります。助は2人のために片足、片目の不自由な身体となっていました。争いの結果、助は金五郎に鎌で殺され、助が連れていた2歳になる女の子は笠に乗ったまま川に落ちて、そのまま流れてしまいました。
その10数年後、その女の子累は美しく成長し絹川家の養女となって御殿勤めをしていました。あるとき美男の与右衛門を見そめて恋に落ち、身ごもります。ところが与右衛門とは仮の名、実は親の敵の金五郎が世間を憚り、そう名乗っていたのです。逐電した与右衛門を追ってきた累の顔は、助の祟りで醜く変わり、片足も不自由になります。次に挙げるのは有名な殺しの場で、「色彩間苅豆」の題で清元によって語られます。
成仏せよと無二無三、打って懸れば身をかわしのふ情けなや恨めしや、身は煩悩のきづなにて、恋路に迷ひ親々の、仇なる人と知らずして、因果は巡る面影の、変り果てにし恥づかしさ、悋気嫉妬のくどき事、我を我が身にほれ過ぎし、心の内の面テなや、
無惨にも累は、因縁の鎌で助と同じように惨殺されてしまうのでした。
累の姉、おさえは絹川甚三郎と夫婦になっています。絹川家は主家から預かった「なでしこの茶入れ」を紛失し、おさえ夫婦は行方を尋ねていますが、茶入れ横領を企む与右衛門に、ともに斬り殺されてしまいます。しかし、懐にあった祐念上人の名号のおかげで命を助かり、茶入れも手に入れて帰参の見込みも立ち、仇の与右衛門を討つ、というところで幕となります。
祐天ファミリー31号(H13/4/15)掲載