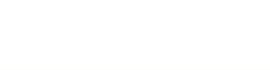

正月28日、増上寺塔頭の芝宝松院(港区)から11霊の供養を依頼されました。宝松院は、祐天上人の随従であった雲洞が6世住職だったことから、祐天寺と縁の深い寺院です。『本堂過去霊名簿』によると、この11霊は在源、在禅、禅翁、英専、英進、頓成、植本、円寿、周観、孝沾、香禅であると思われます。供養に際する祠堂金として200両が祐天寺へ納められました。
3月、郡山藩(奈良県)藩士の庄司金太郎から、海で遭難するも助かったという文書が祐天寺に奉納されました。内容は次のとおりです。
文久3年(1863)6月25日、1、800石積みの漁船住悦丸は、水主17人と金太郎を含む郡山藩士7人を乗せて品川(品川区)を出帆しました。翌日、浦賀(神奈川県横須賀市)に着き、29日には伊豆(静岡県伊豆市)まで乗り出しましたが、風が悪いので2、3里(約8~12キロメートル)戻ったところで2晩停泊しました。
7月2日にいったん出航したものの、やはり風が悪くなったので浦賀に戻り、7日の朝に再び出航しましたが、8日の夜五つ時(8時)過ぎ頃から墨を流したような空模様となり、大波が押し寄せました。金太郎は助かる見込みはないと覚悟を決めて祐天上人を祈念していたところ、大波により船が壊れて海に放り出され、気が付くと海岸に流れ着いていました。一緒に流れ着いた乗組員とともに山を3つ越し、懐中にあった鰹節で飢えをしのぎながら人里へ行って助けを乞いました。そこは阿波国(徳島県)でした。命が助かったのは祐天上人のおかげだと、いつも身に付けていたお守りを取り出して見ると、守り袋の中は空になっていました。身替わりにお立ちになったのかと伏し拝み、以後は日々祐天上人を拝みました。
8月、日本橋室町(中央区)の7代目竹原文右衛門より竹原家先祖代々の位牌と祠堂金50両が納められました。
10月18日、祐天寺の末庵である大岱村地蔵庵(東村山市。享保14年「祐天寺」・「説明」参照)の本尊修復が済んだため入仏供養が執り行われることになり、祐天寺から代僧1人、添僧1人、説法僧1人、伴僧1人、侍2人、陸尺(駕籠を担ぐ人足)4人、草履取1人、説法僧の供1人の計12人が地蔵庵へ向かいました。
地蔵庵はあらかじめ祐天寺から貸し出された幕や内敷、幡、箱提灯などで飾られ、境内には角塔婆も立てられていました。また、同日より20日までの3日間にわたり説法が行われました。
11月4日、檀林の川越蓮馨寺(埼玉県川越市)39世の観随が遷化しました。法号は心蓮社即誉上人行阿善順観随大和尚です。
観随は祐興や学天と同じく順良(知恩院69世)に師事し、祐天上人の法統を受け継いだ僧です。蓮馨寺の再建を果たしたことから、中興の号を諡られました。また観随は、滝山大善寺(八王子市)・静岡宝台院(静岡市葵区)を歴住した霊丈(明治18年「祐天寺」参照)、岩槻浄国寺(さいたま市岩槻区)・浅草誓願寺(台東区)を歴住した戒心、小松川仲台院(江戸川区)・田戸聖徳寺(神奈川県横須賀市)を歴住し祐天寺16世となった霊俊(明治23年「祐天寺」参照)、増上寺三席に列した観哲(明治5年「祐天寺」参照)など、優れた弟子たちを育てました。
明治34年(1901)12月4日に観随の遺骨は、祐天寺17世愍随により蓮馨寺から祐天寺へ移され卵塔が建立されました。この卵塔にはのちに、明治16年(1883)5月2日に遷化した戒心(法号は摂蓮社善誉上人護法阿愚順戒心大和尚。明治6年「祐天寺」参照)と明治36年(1903)11月3日に遷化した霊俊が合祀されました。
7月19日に起こった「禁門の変」(「事件・風俗」参照)により京都河原町(京都市中京区)の長州藩(山口県)藩邸などから出火し、811町と1村、家屋2万7、513世帯、公家屋敷18、武家屋敷51、京都東本願寺(同市下京区)や嵯峨天龍寺(同市右京区)などの寺社253、土蔵1、207と市街の3分の2が焼失しました。
この月、知恩院は兵火を恐れ、ひそかに宗祖法然上人像を御影堂から本地堂(勢至堂)に移し、昼夜勤番していました。
6月5日夜、京都三条の旅宿池田屋に潜伏していた長州藩士を中心とする尊王攘夷激派の志士を、新選組(「解説」参照)が襲撃する事件が起こりました。新選組局長の近藤勇(「人物」参照)は、表口と裏口に3人ずつ隊士を配置すると、わずか4人で池田屋に突入。途中1人が負傷、1人が持病の結核による喀血で戦線を離脱したため、2人のみでの戦闘となります。やがて別働隊の隊士も駆け付け、1時間近い乱闘の末に新選組は7人を討ち取り、20数人を捕縛しました。
この事件のきっかけは、前年に起きた公武合体派の公卿と会津藩(福島県)・薩摩藩(鹿児島県)とが対立した「8月18日の政変」です。この朝廷内でのクーデターにより、三条実美(文久3年「人物」参照)ら尊王攘夷派公卿7人が参内・面会を禁じられました。同時に、彼らと手を組んで、天皇が自ら指揮を執って攘夷を行うことを画策していた長州藩も御所の境町御門警備を罷免となり、長州藩の尊王攘夷派の志士たちは7人の公卿とともに帰国。一時は尊王攘夷運動は行き詰まったかに見えました。
しかし、この年になると運動が再燃し、尊王攘夷激派の志士らが御所に放火して混乱に乗じて天皇を長州に奪い去ろうとしていることを新選組が突き止めます。新選組はすぐさまこの情報を京都守護職へ伝え、京都の町中を探索して、計画を企てている志士らを見付け出したのでした。
この事件の功績に対し、京都守護職松平容保(文久2年「人物」参照)から新選組へ褒賞金600両が下賜されました。
「8月18日の政変」以降の長州藩は、天皇を再び長州陣営に付かせるため京都に乗り込もうとする急進派と、それに反対する慎重派とに分裂していましたが、「池田屋事件」の報せを聞くと藩論はいっきに急進派へと傾き、会津藩を討つべく京都へ進軍を始めました。その数は諸隊(文久3年「解説」参照)を合わせて1、600人。それが3隊に分かれ、それぞれ伏見、山崎、嵯峨付近に陣を構えて京都を包囲しました。
そして7月19日の早朝、蛤御門において、ここを守る会津藩と長州藩とが衝突。同時に中立売御門を守る福岡藩(福岡県)、境町御門を守る越前藩(福井県)との間でも、それぞれ長州藩との戦闘が始まりました。中立売御門、蛤御門から天皇の住まいである禁裏(御所)まではわずかな距離でしかありません。禁裏への侵入を阻止するため乾御門を守る薩摩軍も駆け付け、ここでは激しい戦闘が繰り広げられました。劣勢になった長州藩は天王山へと逃亡し、完敗しました。この戦火は京都の町全域に広がり、大勢の罹災者を出しました。禁裏に兵を向けた長州藩は朝敵と見なされ、これが長州征伐(慶応2年「事件・風俗」参照)の端緒となるのです。
2月、市村座において河竹黙阿弥作の歌舞伎『曽我綉侠御所染』が初演されました。柳亭種彦(文政12年「人物」参照)作の草双紙『浅間嶽面影草紙』の後編「逢州執着譚」を脚色したものです。原作および芝居とも京都五条坂の廓を舞台としていますが、黙阿弥は江戸の人々にとってなじみ深い吉原仲之町の話として書きました。
奥州浅間家当主の巴之丞には、時鳥という愛妾がいました。百合の方(巴之丞の姑)は2人の関係を憎み、巴之丞が都在番中に時鳥を惨殺しますが、その菖蒲の咲く池端での殺しの場面は美しく描かれ、歌舞伎の残酷美をよく表しています。
時鳥の姉妹である忘貝は悪者により都の五条坂の廓に売られ、逢州と名乗っていました。巴之丞は時鳥に似た逢州に惹かれ、廓へ通い詰めます。逢州の朋輩のさつきは元浅間家の腰元でしたが、同じ家中の武士須崎角弥と不義をしたため逢州と同じ廓に身を沈めていました。また、主家を追放された角弥は御所の五郎蔵と名乗り、侠客となっていました。
五郎蔵のライバルでさつきに横恋慕する浅間家の旧臣星影土右衛門は、百合の方とともにお家横領を企てていました。五郎蔵が主君であった巴之丞の廓遊びの金策に悩んでいるのを知ったさつきは、土右衛門から金を手に入れようとし土右衛門になびくそぶりを見せます。これをさつきの愛想尽かしと誤解して逆上した五郎蔵はさつきを斬りますが、それは人違いで逢州でした。
さつきは五郎蔵にいきさつを話し、2人は胡弓と尺八を奏でながら心中します。
この2人の心中の場面は、主演で五郎蔵役の4代目市川小団次が「何か私が困るような新案を立ててくれ」と黙阿弥に依頼してできたもので、腹を切ったのちに息も絶え絶えに尺八を吹くという趣向でした。非常に評判が良かったものの2年後に小団次が亡くなり、のちに黙阿弥はこの場面について「誰が演じても失敗に終わり、手を出す役者がいなかった」と述べています。しかし、明治3年(1870)以後に5代目尾上菊五郎が4回も復演し、彼の没後は15代目市村羽左衛門の当たり芸となりました。
農民から幕臣、そして罪人へと、近藤勇の人生はまさに波乱に満ちています。武蔵国多摩郡上石原村(調布市)の豪農の家に生まれ、幼名を勝五郎と名付けられた勇は、父から昔の英雄の話を聞くことが好きな子どもでした。なかでも『三国志』の関羽に憧れ、よく父に「関羽はまだ生きているの」と聞いていたそうです。そんな勇の興味は自然と剣術へと向かい、15歳のときに兄とともに天然理心流の試衛館へ入門。その翌年には、試衛館の道場主である近藤周助の養子となりました。
周助が勇を養子に迎えた経緯にはこんなエピソードがあります。勇の父が留守のある夜、家に盗賊が侵入しますが、すぐにこれを捕らえようとした兄を「賊は入ったばかりのときは気が立っている」と勇は抑え、賊が盗品を持って立ち去ろうとしたときに兄とともに飛び出すと、賊は驚いて盗品を投げ出して逃げました。追い掛けようとする兄を、勇は再び引き止め「窮鼠猫を噛むと言う。何も盗まれなかったのだから放っておこう」と言ったそうです。この話を聞いた周助は勇の冷静沈着さに感心し、ぜひ養子にしたいと思ったということです。
やがて道場を任されるようになった勇のもとには、沖田総司や藤堂平助、永倉新八などが集まり、けいこが終わったあとに彼らはいつも、国の行く末を憂いて議論を交わしていたと伝えられています。
万延元年(1860)に天然理心流の宗家を継ぎ、近藤勇と正式に名を改めると、同年に結婚。普通であれば、勇はこのまま穏やかな人生を送れたはずでしたが、文久3年(1863)に大きな転機が訪れました。将軍家茂上洛に伴い、京都治安維持の警備を担う浪士隊を募集するという話が飛び込んできたのです。勇や総司、そして土方歳三らは喜んでこれに参加し、京都へと向かいました。勇30歳の春のことでした。
上洛後、勇は壬生浪士組の結成や芹沢鴨との抗争を経て、新選組(「解説」参照)を結成。そして新選組の局長となった勇は武士よりも武士らしく生きることを目指し、時には隊士たちを家来のように扱うなど横柄な態度を取ることもあったそうです。そして慶応3年(1867)6月には、「池田屋事件」や「禁門の変」(「事件・風俗」参照)などでの働きが評価され、新選組は勇の念願だった幕臣へと取り立てられました。しかし、すでに徳川の世は終焉を迎えており、明治元年(1868)に「鳥羽・伏見の戦い」(明治元年「事件・風俗」参照)が勃発すると、勇ら新選組は賊軍となって戦わざるをえなくなったのです。
それでも勇は自分の信念を曲げることなく、錦の御旗を掲げて進軍してくる官軍に対し、最後まで戦うことをやめませんでした。勝沼(山梨県勝沼市)での戦闘に敗れたのち、流山(千葉県流山市)に陣を構えます。ここで再び新生新選組を結成し、官軍に攻め入られようとしている会津へ、一刻も早く向かおうと考えていました。しかし、この動向を官軍に知られ、勇に新選組の解隊と、板橋(板橋区)にある官軍の東海道軍総督府への出頭が命じられます。このとき、勇は潔く切腹をするつもりでした。しかし、試衛館時代からの仲間である歳三の説得により思いとどまり、総督府へ出頭しました。
板橋で斬首された勇の首は京都の三条河原にさらされ、のちに故郷である多摩に葬られました。享年35歳でした。