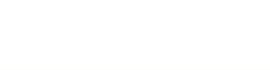

正月7日、土佐藩(高知県)山内家に女子が誕生し、のちにその誕生日と「辰歳女子」と刻まれた地蔵菩薩坐像付き石塔が祐天寺に建立されました。
この女子は、12代藩主豊資の息女の嘉年(母は側室、沢田貞道の娘)と考えられます。嘉年は安政6年(1859)正月25日に徳大寺実則に嫁ぎ、明治12年(1879)3月27日に逝去しました。
2月、祐義が祐天寺12世として北見慶元寺(世田谷区)より入院しましたが、4月29日に遷化しました。法号は法蓮社王誉上人相阿愚海祐義大和尚です。祐義は鴻巣勝願寺(埼玉県鴻巣市)17世祐頓(祐天上人の随従)の弟子でした。
7月13日、松崎浄泉寺(静岡県賀茂郡)19世順海が祐興(慶応2年「祐天寺」参照)と名を改めて、祐天寺13世となりました。
11月10日、11代将軍家斉御台所の広大院が逝去し、祐天寺に位牌が納められました。法号は広大院殿従一位超誉妙勝貞仁大姉です。
広大院は薩摩藩(鹿児島県)8代藩主島津重豪の息女で茂姫と言いました。祖母にあたる竹姫(享保10年「人物」参照)の遺言により、当時はまだ一橋家の嫡子であった家斉と婚約し、9歳で一橋家へ輿入れします。しかし、家斉が10代将軍家治の養嗣子となり11代将軍となったことから、広大院は御台所となりました。
祐天寺には広大院が寛政10年(1798)に流産した男児(寛政10年「祐天寺」参照)が埋葬されており、文政12年(1829)にはその33回忌も行われています。また広大院は、広島唯称庵(現存せず。天保14年「祐天寺」参照)の永世什物となっていた祐天上人名号軸の寄進者と考えられ、竹姫の信仰を受け継いでいたことがわかります。
この頃、日高生蓮寺(和歌山県日高郡)に祐天上人名号石塔が建立されました。中央に祐天上人、向かって右に川辺来迎寺(同県同郡)13世月誉、左に徳本の名号が、それぞれ彫られています。月誉の活躍時期から、この頃の建立と推測されます。
7月10日、鎌倉光明寺(神奈川県鎌倉市)89世智典が台命により増上寺65世となり、大僧正に任じられました。
11月10日、広大院が逝去したため、23日に智典が導師を勤めて法会を開白し、25日に結願しました。翌年、江戸城大奥松の御殿が増上寺に寄進され、方丈・書院の隣に再建されました。また、同寺では安国殿本坊、三門、方丈などの修理をし、弘化4年(1847)には鎌倉円覚寺(同県同市)の仏舎利を増上寺山内浄運院(港区)に迎え、結願会を行いました。 嘉永4年(1851)2月22日、智典は重病のため隠退を願い出ますが慰留され、再度願って3月16日に許されました。文久3年(1863)5月23日に遷化しました。
6月29日の夜八つ時(午前2時頃)、小伝馬町(中央区)の牢屋敷から不審火が起こり、やがて猛火となって燃え広がりました。
火事により猛火が牢屋敷に迫った場合、囚人たちは一度解放されることになっていました。そこで囚獄(牢屋奉行)が「一同の者この火事につき解放す。銘々神妙に本所回向院(墨田区)へ立ち退くべし。ついてはそれぞれ弁当を与うるにより3日間のうちにその係り役所へなりとも申し出ずべし」という沙汰を下しました。
こうして解放された囚徒が3日以内に戻ったときは、罪1等が減じられました。しかし火事に乗じて逃亡の挙に出た場合は、捕縛しだい死罪です。
このときの出火では63人の囚人がいったん解放されましたが、このうち座敷者(揚がり座敷)1人、雑人(一般牢)6人が戻ってきませんでした。この7人の中には高野長英(天保7年「人物」参照)が含まれており、この火事は長英が牢内雑役の栄蔵に金を渡し火付けを依頼して起こしたものと言われています。
5月、水戸藩(茨城県)9代藩主徳川斉昭(天保元年「人物」参照)が幕府から隠居・謹慎を命じられました。前年の天保14年(1843)には藩政が行き届いているとして、将軍家慶から異例の表彰を受けていただけに、この処分は青天の霹靂でした。
処分の理由には斉昭の政治が気ままでおごり高ぶりがひどく、幕府の制度に触れることもあったことなどが挙げられています。しかし実は、斉昭が行った寺院への統制(天保14年「寺院」参照)が仏教界に大きな波紋を投じたことが最も大きな要因と思われます。寺院の中には幕府や皇室との関係が深いところもあったために、斉昭の行動を幕府としては無視できなかったのです。
斉昭は江戸駒込(文京区)の水戸藩邸に謹慎となり、斉昭の長男でわずか13歳の慶篤が10代藩主に就任しました。「甲辰の国難」と呼ばれるこの事件により、藤田東湖(安政2年「人物」参照)や戸田忠敞など、水戸藩内で行われていた改革(天保元年「事件・風俗」参照)の立役者たちも斉昭とともに処分を受け、水戸藩内は一気に混乱の深みに落ち込んでいきました。
好花堂野亭によって『浄土宗回向文和訓図会』上中下3巻が著されました。上巻は「円光大師略伝」、中巻は「善導大師二河白道之譬喩并大意」や「看経之心得并焼香文」、「百萬遍念仏之起源」、下巻は「元祖大師一枚起請略解」など浄土宗の法をさまざまな逸話・伝説を交えて説明した勤行の解説書となっています。
中巻の「利剣名号の文」では利剣名号の由来とともに、「かさね」の伝説から累と与右衛門の因果応報を例とし、利剣名号が無明、果、業因(すべての苦をもたらす原因)を滅ぼすと説いています。さらに、累の霊の解脱は祐天上人の名号の功徳によるものだと説き、念仏を尊ぶべきだとしています。
松崎慊堂は肥後国益城郡木倉村(熊本県上益城郡)の農家に生まれましたが、幼い頃から四書五経を読みこなすほど聡明だったそうです。そこで、10歳になると父の勧めに従って出家しました。やがて寺の生活になじんでくると、経典の勉強だけでは飽き足らなくなり、僧侶になるよりもいっそ儒学を修めて学者になりたいと考えるようになります。慊堂の勉学への欲求は日に日に増し、ついに寺を飛び出し上京したのは15歳のときでした。
江戸では浅草称念寺(台東区)に身を寄せ、寺の雑務をこなしながら儒教の勉強に励みました。称念寺の住職は慊堂の非凡な才能を見抜き、行く行くは称念寺を継いで欲しいと考えていましたが、慊堂の儒学への志が固いことを知ると、良き理解者となって昌平坂学問所(寛政9年「事件・風俗」参照)へ通うことを許しました。学問所では林述斎からも才能を認められ、のちに官学の総長とも言われた佐藤一斎と学識を競い合うなど、充実した日々を送っていたようです。
享和2年(1802)に掛川藩(静岡県)の教授として招かれると、しばしば藩政にも意見を求められるほど重用され、また文化8年(1811)の朝鮮通信使来聘の際には、述斎の求めに応じて対馬(長崎県)に赴き、通信使の応接にもあたりました。
こうして学者としての慊堂の名が世間に広まると、慊堂の故郷である熊本藩から儒講として招きたいという申し出がありました。慊堂自身に故郷へ帰りたいという気持ちがなかったわけではありませんが、慊堂の性格上、掛川藩の恩義に背くことはできず、両藩の間で進退に窮したことなどから江戸郊外の羽沢(渋谷区広尾)に隠居します。以後亡くなるまでの23年間は、家塾「石経山房」を開いて弟子の育成に心血を注ぎました。
隠居したとは言え、慊堂の交友関係は広く、学問への情熱も衰えを見せませんでした。50歳を過ぎた頃からは朱子学のみならず漢学の研究にも力を注ぎ、唐の『開成石経』に校訂を加えて出版するなどの功績を残しています。天保13年(1842)には幕府から表彰され、将軍家慶にも謁見を許されるなど華々しい活躍を遂げました。
学問に対しては真っ直ぐで妥協を許さない慊堂でしたが、人を疑うということを知らない性格のため、特に若い頃は学友の借金の保証人になって苦労したり、妻にさえ裏切られるなど失敗が少なくありません。しかし、蛮社の獄(天保10年「事件・風俗」参照)に際して、なり振り構わず弟子の渡辺崋山(天保12年「人物」参照)の助命嘆願に奔走した話は有名であり、その情の厚さゆえに多くの人々から愛されました。
一流の学者でありながら時には情に流され、運命に翻弄され続けた慊堂は74歳でこの世を去り、目黒長泉院(目黒区)に葬られました。