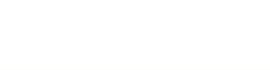

5月、深川常照院(江東区)に祐天名号付きの長谷川家供養塔が建立されました。長谷川家は松坂(三重県松阪市)の木綿商で、大伝馬町(中央区)に江戸店を構える豪商でした。長谷川本家は松坂清光寺(安政元年「祐天寺」参照)の檀家総代であることから、祐天上人に信仰を寄せていたものと考えられます。
6月、祐梵は祐天上人名号軸に真筆である旨を裏書きしました。現在この名号軸は深川正源寺(江東区)に所蔵されています。
7月、伊勢松尾観音寺(三重県伊勢市)に祐天上人名号石碑が建立されました。この石碑は森島文平という商人の供養碑です。
文平は酒造業を営む豪商でした。人格者で、不当の益をむさぼることをせず、毎月3度の休業日を定めて茶飯の饗応をし、子弟らを一堂に集めては和漢の格言をていねいに教えたと言われます。この石碑は文平の没後に、文平から薫陶を受けた有志12人によって建立されました。
9月29日、目黒筋へ将軍家慶の御成があり、祐天寺が御膳所となりました。その際に家慶は、本尊祐天上人坐像をはじめとする寺内の宝物を上覧しました。
この年、『東都歳事記』が刊行されました。祐天寺はしだれ桜や紅葉の名所として本書に紹介され、毎月15日に別時念仏を修行していることや西方六阿弥陀の第6番、江戸南方四十八所地蔵尊参りの第1番であること、3月3日には雛人形を飾ることなどが事細かに書かれています。また、当時は開山忌を10月1日に行っており、その様子が次のように記されています。「午の刻(正午頃)、弥陀仏の像、開山の像、祐海上人の像各輿に移し、本堂より音楽にて境内を巡行し、住職は歩行にて十念を授く。扨弥陀仏の像は弥陀堂へ安置し住持礼拝あり。両上人の像は元の如く本堂へ帰坐なしまゐらす」。
明和2年(1765)に発刊した『誹風柳多留』(明和2年「出版・芸能」参照)の刊行が、この年終了しました。左記の句をはじめ祐天上人、祐天寺に関する句も多く掲載されています。
祐天寺わざわひの根をおがませる
祐天のにせなど貰ふ新世帯
祐天はかさね〱の礼をうけ
祐天は手品遣いか釼をのみ
6月10日、鎌倉光明寺(神奈川県鎌倉市)89世順良が、台命により知恩院69世となり、翌年、大僧正に任じられました。天保12年(1841)2月18日、仁孝天皇より先帝光格天皇の遺品として白銀、花瓶および青貝花台が下賜されました。順良は6年余り在住し、弘化元年(1844)11月に老齢のため退隠し、三条天性寺(京都市中京区)に隠棲しました。
この年、大和国(奈良県)の農民中山みき(「人物」参照)が、親神である天理王命の天啓を受けて天理教を創唱しました。天理教の信仰生活は「陽気ぐらし」と言って、人間が等しく神の子として「一列きょうだい」となり助け合うところに実現すると説いています。
天理教の原典は、みきが筆をとって親神の教えを記した『おふでさき』と『みかぐらうた』『おさしづ』の3点から成ります。みきの死後、天理教はたび重なる国家権力の弾圧から逃れるために、神道直轄天理教会という形で認可を受けます。しかし、明治29年(1896)には内務省から天理教弾圧を目的とした秘密訓令が出され、教義・儀礼の改変を余儀なくされました。
原典に込められたみきの精神とはほど遠いものとなった天理教でしたが、昭和20年(1945)以降は2代真柱の中山正善のもと「復元」運動が行われ、みきの教えが再び全面に出されるようになりました。
この年、緒方洪庵(嘉永5年「人物」参照)が大坂瓦町に蘭学塾を開校しました。洪庵の号に因んで適々斎塾あるいは適塾と呼ばれます。やがて門人が増えて手狭になったために、天保14年(1843)には過書町(大阪市中央区)に移転しました。洪庵没後の元治元年(1864)までに適塾の門人となったのは637人、彼らの出身地は全国に及びます。
洪庵は細かい塾則は定めず、塾生には自由な生活をさせ、各自の努力によって実力を養わせる方針を採りました。そのためか、塾生たちはひと筋縄ではいかない者ばかりで、町のあちこちで大げんかの真似をしてみたり、料理茶屋で猪口や小皿などを盗んできたりと、さまざまな「悪戯」をしていたそうです。
しかし学問に関しては皆、寝食を忘れるほどに没頭しました。塾生の起居にあてがわれた40畳ほどの大部屋には常に50~60人近い塾生がおり、昼夜の区別なく本を読み、疲れて眠くなれば机に突っ伏して眠りました。
この塾からは福沢諭吉(明治5年「人物」参照)をはじめ佐野常民、大鳥圭介など、幕末や明治維新期に活躍した人物が多く輩出されたことからも、適塾が日本の近代化に与えた影響は計り知れないと言えるでしょう。
8月、都々逸坊扇歌が牛込藁店(新宿区)の寄席で念願の晴れ舞台を飾りました。扇歌が34歳のときのことです。
扇歌は本名を岡福次郎と言い、常陸国佐竹村(茨城県常陸太田市)に生まれました。幼少の頃から音曲を好み、20歳を過ぎてからは江戸へ出て、按摩のかたわら唄を歌って生計を立てていたようです。そして29歳のときに船遊亭扇橋に拾われてその弟子となり、扇歌を名乗りました。
扇歌の唄は、七・七・七・五調の三味線とともに歌われる俗曲です。扇歌は単に歌うのではなく、客席からもらった題に「何が何してなんじゃいな」と拍子を取りながら即興で歌い返す、謎解き歌を得意としました。扇歌の美声と機知に富んだ謎解き歌の新鮮さに人々は魅了され、押し寄せた客で寄席の床が抜けてしまったという逸話があるほどの人気を博します。
しかし、天保の改革に対する反感から世相や幕府を諷刺する唄を歌ったことで、ついに江戸を追放されてしまいます。それでも上方を放浪しながら歌い続けたため、やがて扇歌の唄は「都々逸」の名で全国に普及していきました。嘉永5年(1852)に49歳で生涯を閉じた扇歌の辞世の唄です。
都々逸も 謡いつくして 三味線枕
楽にわたしは 寝るわいな
天理教(「寺院」参照)の教祖である中山みきは、大和国(奈良県)の豪農の娘として生まれました。内向的な少女で、習字・裁縫・細工物に熱中することが多かったようです。この頃のみきに影響を与えたのは、自家の宗旨である浄土宗でした。みきは10歳くらいで和讃(仏菩薩の徳や教えなどを和語で讃えたもの)のほとんどを暗唱し、寺参りを楽しみにするような子どもであったと言われています。
12歳のときに「尼になりたい」と親に願いましたが許されず、13歳で親戚の中山家の嫡男善兵衛に嫁ぎます。みきは結婚の条件として朝夕の念仏勤めと寺参りの自由を申し出ます。19歳のときには五重相伝を受けました。
結婚してからのみきの生活は、地主の妻といえど決して楽なものではありませんでした。作男とともに田植え、草取り、稲刈りなど、たいていの農事はやってのけました。結婚3年目の16歳にして、「へらわたし」(主婦権を姑から譲られること)を受けたほどで、みきの働きぶりは村でも評判でした。
みきは1男5女をもうけますが、次女と3女を亡くします。また、長男の秀司が原因不明の足痛に悩まされます。医者にも診せましたが治る気配がなく、山伏の市兵衛に祈祷を頼み、寄加持を繰り返しました。天保9年12月23日、いつも加持台を勤める女が不在だったため、みきが勤めることになります。みきは神憑状態となり、それは3日3晩続きました。そのときに、「天の将軍」と名乗る神が憑依し、みきの体を「神の社」としてもらい受けることを宣言します。善兵衛が神の求めを承知し、神憑状態はようやく収まったのです。その日、26日が天理教立教の日とされています。みき41歳のときでした。
みきは神のよりしろとなってから亡くなる90歳まで、神の言葉を実践し続けました。最初の20年間は「貧に落ちきれ」という神の言葉どおり、いっさいの財産を施し続け、最後には先祖代々続いた田畑までも売り払ってしまいます。そうした行動は家族や親戚にすら、とうてい理解されるものではありませんでした。
また、みき自身も神憑状態から醒めると、いく度も池や井戸へ身投げをしようと試みるなど、神と人間との間の内面的矛盾に対し激しく葛藤します。しかし、農村の最下層の貧窮生活を体験することにより、初めて全身で民衆への愛情とヒューマニズムに貫かれた平等観を捉えるに至ります。
その後も家族には理解されませんが、近隣の者たちからは安産の神さまとして信仰を集め、また治病によっても信者を集めるようになります。
しかし、信者が増えるにしたがって、既成宗教や国家権力から弾圧を受けることとなります。高齢にもかかわらずみきは18回前後も投獄されますが、そのときも獄中生活を権力者たちへの布教の機会と捉え、監獄に出向いたと言われます。みきは決して弾圧に屈することなく、豊かなヒューマニズムに貫かれた平等観を説き続けます。
みきの説いた天理教は、この時代の民衆の生活に根ざした切実な要求にほかならず、そこには民衆の間から生まれてきた新宗教の成立につながる人間観の先進性が見られます。