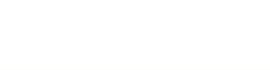

2月19日、紀州藩(和歌山県)11代藩主徳川斉順の側室於ルキが流産しました。その子どもの法号は明元院香陽浄満大童女です。のちに斉順の子女たちの供養塔が祐天寺に建立されますが、その際に合祀された1霊です。
2月、祐麟は『真宗浄土精華集』を著しました。これは祐天寺独自の伝法書です。
『江戸名所図会』は江戸と江戸近郊の絵入り地誌です。全7巻20冊のうち、3巻10冊までが天保5年(1834)に、そして残りの4巻10冊がこの年に刊行されました。祐天寺については3巻に、「常行念仏の道場にして、鉦鼓の声は山林に谽谺せり」と絵入りで紹介されています。
また、3月に祐天寺で雛人形を飾る習慣があった由来も、以下のように記されています。元禄年中(1688~1703)、祐天上人が5代将軍綱吉の前で法問する姿を側室のお伝の方(元禄5年「人物」参照)が像に刻みました。これは長悦の像(宝永4年「祐天上人」参照)と名付けられ、鶴姫(延宝5年「人物」参照)に進ぜられて雛祭りの席に一緒に飾られていましたが、のちに祐海がたまわって祐天寺に納められました。このため祐天寺では毎年3月にこの像を飾って、雛祭りの儀式を行っていたということです。
6月1日、小石川伝通院(文京区)54世徳翁が増上寺62世となり、大僧正に任じられました。天保9年(1838)9月3日には江戸城紅葉山台徳院殿霊屋遷座供養が行われ、徳翁はその導師を勤め、のちの12代将軍家慶(天保8年「人物」参照)より白銀150枚をたまわりました。
天保10年(1839)9月10日に隠居し、同12年(1841)5月3日に76歳で遷化しました。
飢饉の際に米の代わりとなるような食物のことを救荒作物(または食物)と言います。享保の虫害飢饉(享保17年「事件・風俗」参照)の際に青木昆陽(享保20年「人物」参照)がサツマイモ(甘藷)を救荒作物として奨励したことは有名ですが、この飢饉以降、幕府や諸藩はたびたび食用可能な野生植物を通達しました。
天明の大飢饉(天明3年「事件・風俗」参照)以降は「救荒書」と呼ばれる文書類が流行しました。特に米沢藩(山形県)9代藩主上杉鷹山(文政5年「人物」参照)が領内に配布した『かてもの』は有名で、ここに挙げられた食物で作られた料理は、米沢の郷土料理へと受け継がれています。
天保の大飢饉(天保4年「事件・風俗」参照)の際には、江戸の蘭学者たちにより飢饉の対策研究会である尚歯会(天保3年「解説」参照)が作られました。この会の研究の成果は、天保7年に高野長英(「人物」参照)が『二物考』にまとめています。この本の中で長英は救荒作物として、荒れ地でも育つ早生ソバや、悪天候にも耐えるジャガイモの栽培を奨励しました。
しかし二宮尊徳は、「『救荒書』は学者の空論にすぎず、食べ過ぎれば有害となる危険がある食物も多い」と指摘しています。また、凶荒時は作物全般の発育が悪いために、救荒作物も飢饉への実益は少なかったようです。
天保の大飢饉がピークに達したこの年、「おいなァりさァんー」という呼び声とともに、油揚げの中に雪花菜を詰めた稲荷鮨を売り歩く行商人の姿が、江戸のあちこちで見られるようなりました。当時は大きな稲荷鮨を切り売りし、1切れ4文(銭湯で体を洗うのに使われる米糠が同じく4文であった)という安さと、栄養満点なことで人気を得ます。なかでも、石町十軒店(中央区)の次郎右衛門という稲荷鮨売りは「次郎公」の愛称で呼ばれ人気を博しました。
稲荷鮨の売り方には屋台見世と、桶を担いで売り歩く振売りがありましたが、目印の幟や提灯には宝珠と「いなりすし」の文字にキツネの顔、鳥居などが描かれていました。このように稲荷信仰と結び付けられたのには、稲荷鮨がキツネ色の油揚げでできているからとする説や、キツネが油揚げを好むからとする説などさまざまです。
天保末年(1843)頃になると、油揚げの中に木耳や干瓢を刻み込んだ飯を詰めて売り出されるようになり、わさびじょう油で食べていたことが知られています。
豊後国日出藩(大分県)の元家老であった帆足万里が、日本初となる自然科学の入門書『窮理通』を著しました。
万里は三浦梅園(天明4年「人物」参照)の影響を受けて、西洋の自然科学に興味を持ちます。文化7年(1810)、万里33歳のときにはすでに『窮理通』を一応完成させていました。しかし、漢訳本を参考にしたところ誤りが多かったため、万里は独学でオランダ語を学び、原著を基に書き直したのです。そして万里59歳のこの年、約20年の歳月を経て13冊もの蘭書を引用した『窮理通』を完成させたのでした。
『窮理通』は全8巻から成り、暦の起こりではニコラウス・コペルニクスの地動説について、引力の説明ではアイザック・ニュートンの法則が紹介されるなど、当時の日本にあってこれほど西洋科学に理解を示した書物はありませんでした。
蘭学者として波乱の人生を歩んだ高野長英は、奥州胆沢郡水沢(岩手県奥州市)に、領主の家臣後藤実慶の3男として生まれました。名を譲と言います。9歳のときに父が死去すると、長英は母の実家である高野家の養子となりました。高野家は医学者一家で、祖父は漢方医学を、養父は蘭方医学を学んでおり、長英は2人から学問の手ほどきを受けたと言います。
向学心旺盛な青年となった長英は、17歳のときに医学修業のため江戸へ出ました。実兄の江戸留学に同行する形で、養父の反対を押し切っての遊学でしたが、江戸における長英の生活は苦難の連続でした。寄宿先や勉学先がなかなか見つからず、さらに兄が病に倒れ、長英は按摩や蘭書の翻訳などをして生活費を稼いだと言います。やがて吉田長淑のもとで本格的に蘭学の勉強を始めますが、看病のかいなく兄が死去し、住まいも類焼により失い、さらに師の長淑が急逝します。しばらくは長淑の塾の経営に携わりましたが、折しも長崎オランダ商館のフィリップ・シーボルト(文政7年「人物」参照)の噂を聞いた長英は、長崎へ留学して鳴滝塾へ入門。ここで長英が書き上げた多くの論文はシーボルトから高い評価を受け、長英は「ドクトル」の称号を授けられました。
文政11年(1828)にシーボルト事件(文政11年「事件・風俗」参照)の連座を逃れて身を隠した長英は、事件のほとぼりが冷めるのを待って江戸に戻ると、町医者として診療のかたわら、日本最初の生理学書『医原枢要』をはじめとする多くの書物を著しました。この頃に渡辺崋山(天保12年「人物」参照)と出会い、蘭語が苦手だった崋山のために蘭書の翻訳を行ううちに、長英も外交や政治について興味を抱くようになります。そして幕府の外交政策を批判した『戊戌夢物語』を著しますが、この書がもとで長英は永牢の刑に処されました。いわゆる蛮社の獄(天保10年「事件・風俗」参照)です。長英が36歳のときでした。
小伝馬町牢屋敷(弘化元年「解説」参照)での長英は、医者としての腕を買われて牢名主にまで取り立てられましたが、狭く風も通らない牢屋の環境は耐えがたいものでした。弘化元年(1844)に牢屋で起きた火事(弘化元年「事件・風俗」参照)に乗じて逃亡しますが、これは長英が牢内で雑役をする男に頼んで放火させたものと言われています。
逃亡後の長英の足取りは定かではありません。しばらく江戸に潜んだのち郷里の実母のもとを訪れ、嘉永元年(1848)には宇和島藩(愛媛県)8代藩主伊達宗城から内密に招かれて兵書の翻訳などに従事したとの記録があります。脱獄囚として全国に指名手配されていた長英は、人目を避ける生活に気分がふさぎ、安眠できずに常に酒を求めて1日3升も飲んでいたそうです。しかしこの生活は長く続かず、幕府が長英の宇和島潜伏を疑っているという知らせを聞き、急ぎそこを旅立ちました。嘉永2年(1849)のことです。
再び江戸に戻った長英は薬品で顔を焼いて容貌を変え、沢三泊と名乗って町医者を開業しました。危険とは知りつつも、それしか生活の糧を得るすべがなかったのです。江戸に潜伏して1年。長英はけが人を装った同心に隠れ家に踏み込まれ、自殺しました。享年47歳。墓は郷里の水沢大安寺にあります。