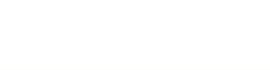

2月14日、江戸城西丸の於さまが逝去し、祐天寺に法号が納められました。法号は寛寿院玉顔妙容大姉です。
於さまは、楽宮(天保11年「祐天寺」参照)のお附きとして、文化元年(1804)に下向してきました。文政3年(1820)に12代将軍家慶の疱瘡平癒を祈願したお札を納める際や、楽宮が流産した明幻院・浄邦院(天保元年「祐天寺」参照)が埋葬された際など、祐天寺にたびたび代参していました。
5月、祐麟が隠退し、祐梵(天保14年「祐天寺」参照)が祐天寺11世となりました。
『本堂過去霊名簿』の「毎月十五日切回向盆中回向」の欄には祐麟・祐梵がそれぞれ執り行った回向の記録があります。それによると、祐麟が在住中の最後に回向したのは天保5年(1834)12月からこの年の5月までの「470霊」です。その後、祐梵が引き続き5月から12月までの「1、473霊」を回向していることから、5月中に住職を交代したことがわかります。
祐麟の代に組織された講には、本堂や諸堂修補のために浄財を喜捨した「三万人講」や、天保2年(1831)に田町(港区)の伊勢屋文蔵が発起人となって始められた「十五日念仏講」などがあります。
また祐梵は天保2年10月から祐天寺入院前までは滝山極楽寺(八王子市)を住持しており、その間に引導した41霊の回向も続けていました。
6月頃、祐麟が天保4年(1833)から編纂していた『明顕山寺録撮要』が完成しました。これは香残(祐天上人の随従)が書き残した『寺録』を基にして、9世祐東までの『日鑑』と2世祐海の記した「明顕山祐天寺永代式條」、および祐麟が増上寺役者を勤めていた折に寺社奉行所から買い請けた「境内帳」の中の祐天寺に関する部分を加筆し、全5巻10冊にまとめたものです。本書には、祐天寺の歴史を後代に伝えるうえで特に重要な事柄が収載されており、当時を知る貴重な資料となっています。
9月、10年間の千部供養を厳修したので、引き続き来年から10年間千部供養を行う旨の願書を、寺社奉行の脇坂中務大輔安董へ差し出しました。翌10月、願いのとおり許可されました。
この千部供養は祐天上人の1周忌より始められ、厳修するたびに次の願書を寺社奉行へ届けて続けられてきました。
11月6日、佐賀無量院(佐賀県鹿島市)18世亮禅が遷化しました。法号は宝蓮社冠誉上人定阿愚性亮禅和尚です。亮禅は無量院に秘宝として伝わっていた祐天上人名号の欠けてしまった「阿」の1字を加筆してもらうため、祐天寺に来寺した僧です。
この名号はもともと無量院13世快雄が祐天上人から授与されたものでした。享保13年(1728)に無量院檀家の松尾喜左衛門の妻ツルが難産で苦しんでいたとき、快雄は「阿」の1字を切り抜いてツルに服させました。すると「阿」の1字を右手に握り締めた男の子が生まれたということです。その子は久助と名付けられて無事に成長し、ツルも寛政元年(1789)正月25日に81年の天寿を全うすることができました。ツルが亡くなった当時、この名号は16世善随が所持していましたが、弟子の亮禅に授けられました。亮禅は「阿」の1字がないことを残念に思い、加筆してもらうことを思い付いたようです。亮禅はツルが亡くなった翌年の寛政2年(1790)8月15日に来寺し、その際に祐天寺6世祐全が「阿」の1字を加筆すると同時に名号の由来を裏書きしました。
この名号はその後、安産名号として所蔵されています。同寺にはこのほかにも祐天上人名号軸や祐天上人木版刷り肖像画がありますが、いずれも亮禅が表具していることから、祐全が亮禅に贈ったものと思われます。
3月に京都東本願寺(京都市下京区)において、御影堂では親鸞聖人像の遷座供養が、阿弥陀堂では遷仏供養会が行われ、御影堂での遷座式には多数の参列がありました。また、阿弥陀堂の遷仏供養会には多くの香奠が寄せられました。
東本願寺の諸堂は文政6年(1823)の火災で焼失し、文政11年(1828)より御影堂、天保2年(1831)より阿弥陀堂の再建が始まりました。再建にあたっては文政7年(1824)に幕府より材木の寄進がありました。
近江国坂田郡国友村(滋賀県長浜市)の国友一貫斎が、自作の望遠鏡(天保10年「解説」参照)で、日本初となる太陽黒点の観測を行いました。期間は正月6日から翌7年2月8日までの158日間、総回数216回の連続観測は、世界的にも類を見ないものです。
一貫斎は、国友鉄砲鍛冶の国友藤兵衛家に生まれ、西洋科学技術への興味から、距離測定器、懐中筆などのさまざまな発明をした人物です。かつて江戸で見たオランダ製の反射望遠鏡に大いに刺激を受け、天保4年(1833)に日本で初めて反射望遠鏡を作り上げました。天体観測を通じてさらに改良を重ねた一貫斎の望遠鏡は、天文学者たちも驚くほど高性能なものとなります。そして、この望遠鏡で太陽のほか木星や月、金星、土星を観測し、それぞれ詳細な観測図を残したのです。
一貫斎は太陽黒点に関する観測記録を『日月星業試留』として書物にまとめ、黒点が火の燃えていない部分であることや、同じ形の黒点はないことなども書き記しました。当時の日本の学者たちの間では、黒点は地上の土気が天に上がり固まったものだと信じられていたため、一貫斎の発見は画期的なものと言えます。
12月、文政年間(1818~1829)から続く出石藩(兵庫県)内での藩政改革を巡る対立が落着しました。江戸時代最後の、幕府による裁断が行われた御家騒動です。
発端は、勝手方頭取仙石造酒が進める質素倹約の政策と、大老の仙石左京が考える藩の産業振興政策との対立でした。造酒がこれまで進めてきた施策により藩は6万両の借金を抱えることとなったため、時の6代藩主仙石政美は左京の政策に賛同し、造酒を勝手方からはずして代わりに左京を勝手方頭取とします。しかし、左京の政策に領民から反発の声が上がったため、左京は退任。さらに、政美の急逝により行われた継嗣の選定会議に、左京が息子を伴って参加したことにより、息子を次期藩主にするつもりなのではないかとの疑惑をかけられます。こうして左京は政治の表舞台からの退陣を余儀なくされ、造酒が再び藩政の主導権を握りました。
しかし、造酒を支持する派内での対立が基で処分を受けて再び失脚した造酒は、落胆のあまり死去。そのため造酒の息子主計は、造酒の死によって政権に返り咲いた左京を再び追い落とそうと画策しました。ところが、左京が幕府老中首座松平康任の姪を息子の嫁に迎えていたため騒動は出石藩内にとどまらなくなり、幕閣の主導権争いへと発展していったのです。
仙石家内紛の吟味を命じられた幕府老中水野忠邦(天保10年「人物」参照)と寺社奉行の脇坂安董はさらなる出世を望み、康任を失脚へと追い込みます。主家横領を諮った罪で左京は獄門、出石藩は領地半減、これに連座して康任も隠居謹慎としました。そして忠邦は老中首座に、安董は異例となる老中への出世を果たしたのです。
天保2年(1831)、寺門静軒(天保2年「人物」参照)は生まれ育った江戸の盛り場の様子を書き記そうと思い付き筆を執りました。
相撲・吉原・芝居などの歓楽、浅草・上野・隅田川などの名所や行楽地、銭湯・髪結床などでの、庶民の自由で活力にあふれる生活の様子が、静軒の豊富な知識を基に独特な漢文体で表現されています。市井で生活する静軒らしく、温かな人間性がにじみ出る一方で、不甲斐ない武士や堕落した僧侶、机上の空論ばかりの儒者たちに対する辛辣な諷刺も含まれています。そのため、第4編を刊行したこの年には風俗を乱す書物として発売禁止になりました。
それでも静軒は執筆を続けたため、天保13年(1842)にはさらに厳しい処分を受けます。しかし、静軒が人生を賭けて著した『江戸繁昌記』は、儒学や仏教思想が根底にあり、単なる風俗誌ではなかったため、漢学者を中心とした読者から熱烈な支持を得ました。
その後、『江戸繁昌記』に追随する形で、中島棕隠の『都繁昌記』や田中金峰の『大坂繁昌詩』など、多くの模倣作品が生まれることになります。
文人画家として知られる田能村竹田は、豊後国直入郡竹田村(大分県竹田市)に生まれました。名は孝憲、字は君彝。竹田のほか、田舎児、老画師などと号しました。兄が病弱だったため、次男の竹田が岡藩(大分県)藩医である父の跡を継いで医学を学ぶことになります。しかし、竹田は22歳のときに医者ではなく儒学者となるよう藩主から命じられました。これは、竹田が藩校由学館で学んでいたときの成績が大変優秀だったためと思われます。由学館に出仕することとなった竹田は、幕府へ納める『豊後国志』の編纂に従事し、その資料収集のために近隣諸郡へ旅行することで旺盛な向学心を満たしていきました。
この頃から竹田は詩や絵画、そして填詞(中国の古典文学の1つ)に興味を抱きます。儒学を学びつつも、竹田は自由な学問に憧れていたようです。そんな竹田の思いを理解し、その才能が開花する方向へ彼を導いたのが、由学館総裁の唐橋君山でした。竹田が谷文晁(天保11年「人物」参照)から画の通信教授を受けることができたのも、君山の紹介によります。
享和元年(1801)に『豊後国志』献上のため上った江戸での生活は、著名な学者たちとの出会いに恵まれ、竹田に多大な影響を与えました。填詞の研究を進め、さらに社会問題への興味も抱くようになった竹田は、父の死により27歳で家督を継いだのちも、長崎や京坂へ遊学しています。およそ2年に及ぶこれらの遊学は、食事もままならないほど金銭的な苦労が多かったようですが、学問を突き詰めたいと考えた竹田は、郷里の上司に毎年10両の借金を申し込んだと言います。そしてこの遊学中に竹田は、自分が進むべきは詩画の道だと決意を固め、文化4年(1807)に郷里へ戻ると、本格的に絵を描き始めました。
文化5年(1808)に描いた「七夕美人図」は竹田が初めて藩主に献じたもので、画業が公に認められるようになったことを示すうえで記念すべき作品です。しかし、儒学者としての使命感も持ち続け、文化8年(1811)と同9年(1812)に藩内に起こった一揆に対して、もっと農民を思いやるようにと藩政の改革を促す建白書を提出しています。ところがこれは採用されず、竹田はついに隠居願いを出し、文化10年(1813)にかねてからの念願であった隠居生活を始めました。
隠居後は各地へ遊歴して文人たちと親交を結びます。なかでも頼山陽は最も気を許し合う友人となりました。山陽を通じて竹田の名声も高まり、同時に竹田の芸術性も成熟します。これまでの中国追従主義とも言える観念を捨てて日本独特の感性を尊重するようになり、穏やかで柔らかい画風を完成させました。
画作のほか著作も『山中人饒舌』『竹田荘師友画録』など多数あり、いずれも竹田の識見の高さを物語ります。享年は59歳。大坂の藩邸で、わが子に看取られて静かに逝去しました。