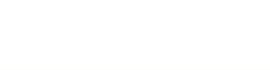

歌人日野資矩は祐水に帰依していましたが、祐水の遷化(文化12年「祐天寺」参照)に遭い非常に悲しみ悼み、阿弥陀経を書写しました。経は7冊に及びましたが、この年正月に祐水の弟子である香堂が1つの箱に取り収め、箱蓋の裏に由来を書きました。
祐天上人100回忌を記念して、この年の3月15日から60日間、本所(墨田区)回向院で開帳を行いました(文化12年「祐天寺」参照)。本尊阿弥陀如来像と祐天上人像そのほかの霊宝を開帳しました。
4月7日、祐東は新湊(富山県)大楽寺が所蔵する祐天上人像に付随した名号の裏書を書きました。表の六字名号は祐天上人の染筆に間違いないという文章のあとに、「四月七日 開帳中」と書かれており、回向院での開帳中にこの裏書を書いたことがわかります。
6月、阿部備中守へ、千部修行の期間に仮日除けを作ることの許可の願い出に伺候しました。役人塩田屯が申し渡したことには、これ以後は願書も請書も西之内紙に書き、増上寺役者の奥印を受けて持参するように、そうすれば即日聞き届けられるだろうということでした。その後は毎年請書を提出するようになりました。ここで言う日除けとは、本堂向拝脇に板戸葺の仮日除けを張り出し、また仮番所2か所、廟所前に仮日除け1か所、水茶屋17か所などを苫葺きで設置するものです。
6月、狼牙落とし名号縁起を大奥へご覧に入れました。狼牙落とし名号とは以下のような話にまつわるものです。ある老女が秩父巡礼に行く前に、祐天上人の庵室へ来て名号を請けていきました。巡礼の途次、仲間とはぐれてしまい、1人山道を歩いていると、狼が襲ってきました。老女が名号を狼の鼻先に差し付けると、狼は牙を1枚落としておとなしくなり、それからは老女を送るように付いてきたという話です。その名号は松村半兵衛の嫁の妙船に伝わり、妙船はその父法眼不角に縁起を書かせ、名号とともに祐天寺へ寄進したのでした。
永代施餓鬼講1万480霊などの切り回向が始まりました。祐天寺過去帳の表記には「回向院出開帳中」と注記があり、回向院の出開帳中に永代施餓鬼講の申し込みを受け付けたものと考えられます。発起頭は伊勢屋安右衛門です。
8月24日、祐水弟子の順昌が寂しました。堺南十万(大阪府)長泉寺に住し、のちに洛東(京都府)井窪寺に住しました。法号は瑞蓮社身誉上人行阿順昌和尚です。
8月、直径7寸9分(約24センチメートル)、高さ2尺6寸5分(約80センチメートル)の蝋燭立てが森川家(「説明」参照)より寄進されました。
この年、町火消しのせ組より額が寄進されました。
4代目の俊胤は致仕後は悠計と号し、また一之顕光英雄院(『寛政重修諸家譜』)と号しました。俊胤は祐天寺に埋葬され(分骨か)、石碑が建立されました。石碑には表面に名号と「一之顕光」の号が彫られ、背面に逝去の年月日などのほか、「となへかし 佛乃御名を 残し置く 法の志るし能 年はふるとも」という、辞世と思われる歌が彫られています。祐天寺に納められている俊胤の法号は英優院殿一之顯光大居士です。その正室である理月院殿遍誉智光大姉も祐天寺に埋葬されました。
7代目の俊孝の法号も祐天寺に納められています。泰崇院殿前紀州大守貫元隆道大居士というものです。俊孝の息女銀姫は祐天寺に葬られています(天明4年「祐天寺」参照)。また、8代目俊知の正室が葬られています。法号は仙壽院殿天誉皓月清光貞照大姉です。
なお、森川家の墓所は昭和19年(1944)に整理されて、現在は祐天寺にあります。
7月に増上寺住職の典海は、塔頭(小院)の13か院に香衣の着用を許可し、以後はこれを13か院における永式法服としました。
当時の増上寺山内には30の塔頭があり、これらの塔頭は上級武士の菩提寺でもありました。この年に香衣着用を許可された13か院は、塔頭の中でも古い歴史を持ち特に格式が高く、塔頭内での指南も勤めていました。
13か院中の池徳院は、祐天上人の伯父の休波が住職を勤めていたこともあり、祐天上人が出家後に初めて上がった寺院でもあります(慶安元年「祐天上人」参照)。
江戸では初物食い(寛文5年「風俗」参照)と並んで、大酒呑みや大食らいの競争が盛んに行われていました。天明7年(1787)には饅頭58個、羊羹7棹、餅30個を平らげたという人や酒20升を飲み干した人がおり、その記録が残っていると言います。また、千住で宿屋を営む中村六右衛門という者が文化12年(1815)に開いた大酒飲み競争の会には、約100人もの参加者があったそうです。参加者には1升入る「万寿無疆盃」、1升5合入る「緑毛亀盃」、2升5合入る「丹頂鶴盃」などの盃が用意され、焼き蟹やからすみなどを肴にして、それぞれ自分の酒量に合った盃で酒を飲み干していきました。この酒合戦で優勝したのは野州(下野国)の佐兵衛という男で、7升5合も飲んだと言います。
その翌13年には両国橋で大酒と大食いの競争が行われ、このときの優勝者は芝口の鯉屋利兵衛という男でした。利兵衛はおよそ19升5合を飲み干したあと、その場に倒れ込み、やがて眼を覚ますと水を茶碗で17杯飲んだという記録があります。このときの会にはほかにも強者が続出し、68歳にして9升を飲み干した人や、7升5合も飲んだあとに帰り道で倒れ、そのまま明け方まで起き上がれなかったという73歳の人、また7升もの酒を飲み干してからご飯3杯を平らげたという人もいました。
一度にこれだけ大量の酒を飲みますと、生命に危険があったのではないかと思われますが、江戸時代の酒は現在の日本酒と比べると味が濃く、通常は薄めて飲んでいたのではないかとも言われます。薄めることによりアルコール度数が低くなり、大酒飲みの記録となったのかもしれません。
いけばな未生流の祖である未生斎一甫の口述を、弟子の無角斎道甫と青松斎義甫が筆記し、宿弥清主翁の協力のもと探養斎一露と桂蔭亭支山が校訂した、未生流の秘伝書です。この年に刊行されました。
一甫は宝暦11年(1761)に旗本山村氏の次男として江戸に生まれ、幼少時より風流を好んで華道を志し、諸流派の奥義を学びました。やがて一甫は諸国遍歴を通して独自の華道理論を形成します。文化4年(1807)頃には大坂で未生流家元の門標を掲げ、弟子も次々と集まり、未生流の前途は明るいかに見えました。しかし、不幸にも一甫は失明してしまいます。それでも一甫は「心眼をもって教えればできないことはない」との信念から口述を続けたため、一甫の華道理論を残そうとする弟子たちの手によって本書は誕生しました。
一甫は中国古代の易経や老荘思想を根底にし、いけばなを通じて悟りを開くという、極めて精神性の高い独自の理論を打ち出しました。そのため他流派にも影響を与え、特に明治維新後は多くの流派が一甫の理論を取り入れました。本書は未生流の入門書としてだけでなく、諸流派の最終的な理論書としても重要な意義を持っています。
江戸末期の浮世絵界において最も大衆的な人気を博した歌川国貞は、江戸本所五ツ目で渡船場を営む角田庄兵衛の一子として天明6年に生まれました。 幼い頃から絵心があり、15歳頃に初代歌川豊国の門に入るとすぐに頭角を現し、豊国の1字をもらって国貞と名乗りました。初筆は文化4年(1807)22歳のときで、滝沢馬琴(文化2年「人物」参照)の合巻『不老門化粧若水』の挿絵とされています。文化・文政期(1804~1829)には、生家に因んだ五渡亭や一雄斎などの画号を使い、合巻の挿絵をはじめとして役者絵や美人画の世界でも活躍しました。役者絵では雲母摺似顔大首絵の「大当狂言之内」、美人画では「星の霜当世風俗」などが代表作です。
天保年間(1830~1843)には英一蝶(元禄11年「人物」参照)の流れを引く英一珪に本格的な肉筆画を学び、香蝶楼という画号を使う時期があります。40歳代半ばから50歳代後半にかけてのこの時期は、制作量も多く画技も円熟して、大衆好みの甘美さでよく受け入れられました。特に文政12年(1829)から天保13年(1842)にかけて出版された、柳亭種彦作『偐紫田舎源氏』(文政12年「出版・芸能」・「人物」参照)の挿絵は好評で、本もベストセラーとなりました。のちに錦絵にした「源氏絵」は国貞の売り物となり、源氏ブームの火付け役ともなりました。
国貞は早くから豊国の正統な後継者であることを自認して、2代目豊国を自称しましたが、実際には豊国の養子となっていた豊重が2代目豊国を継いだため、豊国の画名を襲名するのは弘化元年(1844)まで待たなければなりませんでした。そのため今日では国貞を3代目に数えますが、国貞こそが歌川国芳や歌川広重とともに歌川派全盛期をもたらした功労者であることに変わりはありません。豊国の襲名後は一陽斎と号し、弟子の育成にも積極的であったと伝えられています。当時、国貞が亀戸に住んでいたことから亀戸豊国と呼ばれ、この亀戸派が国芳の玄冶店派と拮抗する形でさらに発展を遂げました。
晩年には濫作に陥り、画質も低俗化していきますが、最晩年に錦昇堂から出された豪華な役者大首絵は気迫に満ちた力作です。浮世絵師としての国貞は遊里の女性を数多く描く一方で、武家や裕福な商家の婦女子を主役とする風俗画も得意とし、さまざまなジャンルを巧みに描き分けて見せる大変器用な絵師でした。
弘化3年(1846)には門人の国政を娘婿に迎え、2代目国貞を襲名させると同時に亀戸の家を譲り、自身は柳島で余生を過ごしました。安政2年(1855)に古希の祝いが催されたときには、お祝いの品が大八車に積みきれないほどだったそうです。浮世絵界の大御所ぶりを垣間見ることができるエピソードと言えます。元治元年12月15日、79歳でこの世を去り、亀戸光明寺に葬られました。