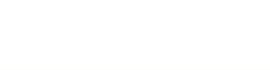

5月10日、幡随院31世観善が寂しました。観善は『祐天大僧正利益記』跋文の著者であり(文化3年「祐天寺」参照)、飯沼弘経寺、鎌倉光明寺を歴住しました。祐天寺過去帳には祐天寺の旧随と記されています。法号は乘蓮社運誉上人直阿自省観善大和尚です。
7月、四谷千部講604霊などの15日切回向が始まりました
8月2日、米屋久右衛門が逝去しました(「説明」参照)。法号は念誉心光恵慶信士です。米屋久右衛門の家は川瀬石町(現、中央区日本橋)にあり、祐天寺に代々多くの法号を納めている信者です。祐東の名号が入った位牌表面には「常灯明施主」と書かれており、常灯明を寄進した人物と思われます。
8月26日、のちに12代将軍となる家慶の子息が逝去しました。祐天寺過去帳に納めてある法号は、玉樹院殿智月英昭大童子です。
9月、大坂源正寺で祐水名号付き経塚が建立されました。住職円随は祐天上人100回忌報恩のためと庫裏と方丈の再建を願って、阿弥陀経10万巻の読誦を発願したのですが、それがすでに14万巻に達したので、それを記念して経を埋める経塚を建立したものです。表面には「當寺開山祐天大僧正」、「経塚」の文字とともに、祐水筆の名号が彫られました。
秋、増上寺の学寮孤雲室が碧雲室と改名されました。「孤は孤独の称がある」として、大僧正在禅が寮主順良に改めさせたのです。
この年に序文が成立した『遊歴雑記』初編に、この頃の祐天寺の様子が描かれています。それによると、本堂の前の石灯籠の際に、扇を開いたような形に1段高く土を盛った部分があり、芝生が生えていたそうです。そして、その要にあたる部分には丸い石があったそうです。この場所にはもともと、祐天寺起立以前にあった善久院が建てられていたそうで、昔仏堂のあった場所を踏み荒らすことは良くないということで芝生が設けられたそうです。
川瀬石町の米屋の家は、元文元年(1736)11月に屋敷を購入したことが資料によって知られます。
7月、大念仏行者と称される徳本(「人物」参照)が小石川伝通院で十念を授けるというので、これを求めて大勢の人々が伝通院に押し寄せました。
徳本は美濃国(岐阜県)や摂津国(大阪府・兵庫県)を中心に教化活動を行っており、その教えのもとにたくさんの念仏講が作られ、その噂は関東にまで及んでいたのです。伝通院境内だけでなく、寺へ至る道々までもが江戸の周辺各地から集まった人々であふれ返り、小石川の水道橋には参詣者の往来のための船が出るほどだったと言います。
11月、増上寺の涅槃門と柵門に下馬札が建てられました。涅槃門は増上寺の北に位置し(港区芝3丁目付近)、柵門は赤羽橋に出るところ(都営赤羽橋駅付近)にありました。両門ともほとんど使用されることがなかったため、下馬札が建てられていなかったのです。しかし、当時の増上寺住職である典海(文化10年「寺院」参照)の代からここを使用するようになったため、下馬札が建てられることになりました。
飢饉は凶作の翌年の春が最も深刻になると言われています。夏になれば麦がとれますが、春には何も収穫するものがないからです。この年の春、前年に大凶作に見舞われた越後国(新潟県)では農民たちが飢饉に耐えていました。凶作になれば領主の年貢収納が減り、領主はさらに厳しく年貢を取り立てるという悪循環の中で、農民たちが生きるためには一揆を起こすよりほかに道はなかったのでしょう。
5月23日、菅田村(新潟県北蒲原郡中条町)で助左衛門を中心とする2、500人余りの農民たちが、地主佐藤三郎左衛門宅をはじめとする富豪たちを襲撃しました。地主や富豪の中には米や金を差し出すことで、打ち壊しを免れた者もいましたが、代官と結託して年貢増徴を図り、高利貸しを行って農民たちを苦しめていた三郎左衛門宅は徹底的に打ち壊されました。また時を同じくして、野口村(新潟県岩船郡荒川町)でも次太郎の呼び掛けに応じた35か村の農民たち2、000人余りが、厳しい年貢の取り立てに抗議するため一揆を起こしていました。そして翌24日には、この両者が合流して蒲原・岩船両郡を中心とした大一揆へと発展しました。
越後国は幕府領・村松藩領・白河藩領・村上藩領・黒川藩領・長岡藩領などが入り組んでいました。そこで、黒川藩では安米の放出や、小作料3か年猶予などの農民たちの要求を認めて鎮め、村上藩は川船を引き揚げて一揆勢の渡河を防ぎ、白河藩は会津藩に出動を要請するなど、諸藩がそれぞれ策を講じて一揆勢の足並みを乱し、26日には多くの逮捕者を出して終結しました。
文化12年(1815)5月、菅田村の助左衛門、野口村の次太郎は遠島を申し付けられ、そのほか一揆に加担した数百人が処分されました。
菊はもともと中国から渡来した植物で、中国では延命長寿の霊草として珍重されていました。奈良時代の漢詩集『懐風藻』に菊酒や菊風を詠んだものが収められていることから、その頃には日本に渡来していたものと考えられています。初めは薬草として渡来したようですが、花の美しさが貴族たちに好まれて鑑賞花となりました。平安時代になると宮廷では重陽の節供の日に菊合わせや菊花の宴が催され、菊を歌に詠み、菊酒を飲んで長寿を願いました。また、皇室の紋章は菊ですが、これは鎌倉時代に後鳥羽上皇が菊を大変に好み、紋様として衣服に付けたことから始まったと伝えられています。
江戸時代に入ると菊作りが庶民にも浸透し、江戸中期頃には栽培技術も発達して多くの品種が作り出されました。文化元年(1804)以降になると巣鴨村(豊島区巣鴨)の菊作り農家を中心として、何かの形に見立てる「大造り」と呼ばれる菊の栽培が盛んになりました。文化11年には現在の菊人形の原型とも言えるような、富士山や屋形船、岩に牡丹、獅子などに模した大造りを見世物として菊祭りが開催され、近在ばかりではなく江戸市中から見物客が押し寄せました。巣鴨村の周辺には茶店などの飲食店が100軒余りもできるほど賑わったと言うことです。
やがて菊人形の流行は巣鴨から団子坂(文京区千駄木)へ移り、なかには木戸銭(入場料)を取るほど評判になったものもありましたが、明治半ば頃を過ぎるといっきに流行は衰えていきました。
滝沢馬琴(文化2年「人物」参照)の長編伝奇小説です。中国の小説『水滸伝』にならった壮大なスケールを持つ作品で、この年の11月から刊行されました。
安房国(千葉県)の領主里見義実の娘伏姫は、手柄を立てた飼い犬の八房の妻となり富山の洞窟に身を隠します。やがて伏姫は、八房の気を受けて懐胎したことをお告げで知り、そのことを恥じて自刃します。その際に8つの玉が空中に飛散しました。物語の発端は、忠臣の金碗孝徳がその玉を求めて旅に出るところまでです。
次いで物語は、玉を持ち、犬の字の付く姓を名乗る八犬士へと移ります。八犬士たちは互いに巡り会い、また離散しながら数々の冒険の末、結城(茨城県)にそろい里見家に仕えます。八犬士の物語は長禄3年(1459)から文明15年(1483)までの、25年間の出来事として書かれています。
その後、八犬士の1人である親兵衛の上京、また八犬士と管領との戦いが描かれますが、八犬士の活躍で里見家が大勝利を収め、八犬士はそれぞれ里見家の姫君と婚姻し、物語は大団円を迎えます。
馬琴がこの物語を書き始めたのは48歳のときでしたが、全106冊が完成した天保13年(1842)には76歳になっていました。まさに馬琴のライフワークとも言うべき作品です。
徳本は、紀伊国日高郡志賀村(和歌山県日高市)に生まれました。幼名は三之丞とい言い、伝説によると、わずか4歳のときに隣家の子どもの死を見て無常を感じ、10歳の頃から念珠を肌身離すことなく念仏を称えていたそうです。また、手習いをする際にも、ほかの子どもたちと違って「南無阿弥陀仏」の六字名号を写すことを好み、家で秘蔵の祐天上人名号をひそかに持ち出してひたすらに写していたとも言われます。幼い頃から出家を望んでいましたが、嫡子であったために両親がなかなかこれを許さず、水垢離や高声念仏の修行を積んだり、同じ日高にある浄土宗の往生寺の大円から五戒を受けるなどの日々を送っていました(天明2年「寺院」参照)。
天明4年(1784)6月、大円を師として得度した徳本は、ようやく念願の出家を果たします。天明5年(1785)に30日間の不断念仏を修してからの徳本は、宗義も学ばず山谷に草庵を結んで五穀を断ち、長髪のまま裸の上から袈裟を着けるという異相で、草庵を各地に移動させながらただひたすらに念仏を称え、荒行を積んでいきました。その期間は20年以上にもわたり、その苦行の中で自ら念仏の教えの要諦を得たと言います。
それからの徳本は、念仏の教化のために各地を巡る旅に出ました。その足跡は故郷の紀伊を中心に、河内国(大阪府)から飛騨国(岐阜県)にまで及びます。この間にも徳本は異相のまま苦行を続けていましたが、享和3年(1803)10月に京の鹿ヶ谷法然院において長髪を剃り落としました。翌11月には江戸の小石川伝通院学頭の鸞洲に招かれ、伝通院住職の智厳から宗・戒両脈を承けます。しかし、山谷にて異相で荒行を積んできた徳本の存在は、江戸の寺社奉行にとって注意すべき者に見えたようで、奉行所から伝通院や増上寺へ、徳本の経歴などを提出するよう指示が来たのです。このとき両寺は、徳本の修行には宗規に反することは何もないとかばい通しました。これは、近年風紀が乱れがちな宗内の僧侶たちに対して、徳本の自然と対峙する厳しい姿から、僧としての本来の在り方に立ち返ることを促そうとする意向と、さらに徳本の庶民に対する教化力に期待するところがあったためと言われます。そして、巧みな説法と、ただひたすらに名号を称えれば良いというわかりやすい教えによって、徳本が教化に訪れた地域では多くの念仏講が生まれていきました。
いったん江戸を離れて故郷の紀伊国を中心とする地域で教化を行った徳本は、文化11年6月に再び江戸へ下向し、小石川伝通院で訪れる人々に十念を授けました(「寺院」参照)。以来、江戸を中心に相模国(神奈川県)や下総国(千葉県)、さらに加賀国(石川県)や越後国(新潟県)へと活動を広げていきます。徳本のいるところは常に十念を求める人々であふれたため、江戸での徳本の滞留地を決めることは非常に難しい問題でしたが、文化14年(1817)に小石川一行院を再興して捨世寺とし、徳本はここの中興開山となることに決定しました。実際に寺社奉行からこれらの許可が下りるのは翌15年のことで、9月には一応の伽藍が整いますが、入仏供養が終わらないうちに徳本は遷化してしまったのです。真新しい本堂で行われた葬儀の導師は、徳本の江戸滞留に力を尽くした増上寺典海が勤め、遺体は一行院に葬られました。徳本独特の丸い書体で書かれた六字名号は「徳本名号」と称され、この名号が刻まれた石塔は全国各地に建立されています。