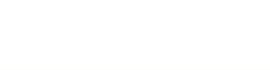

7月17日、永代千部講中碑が墓地に建立されました。施主は寺家村検校を筆頭に、43人が数えられます。それらの人々の職業は商家、大工、曲物師、塗師、石工などで、住む地域は四谷天龍寺前から新屋敷、新町、内藤新宿、上布田、府中に及びます。
9月17日、福島(福島県)大蔵寺に祐天上人名号石塔が建立・開眼されました(文政10年「祐天寺」参照)。裏面に「西国三十三観世音石造造立」と書かれており、大蔵寺境内に残る三十三観音石仏の建立とかかわるものと思われます。
12月13日、昌栁が寂しました。雅山(天明3年「説明」参照)の弟子で、京都西照寺に住しました。祐天寺に納められた法号は轉蓮社輪誉上人願阿昌栁和尚です。
12月15日、祐観が寂しました。祐穏(祐全の弟子。文化元年「祐天寺」参照)の弟子で、車返本願寺(府中市)に15世として住していました。本願寺資料には「城州久世郡(京都府)冨野村城土井産」とあります。祐天寺に納められた法号は在蓮社禪誉上人祐観和尚です。
5月、百萬遍知恩寺54世の祐水(寛政5年「祐天寺」・「説明」、寛政7年・文化7年「寺院」参照)が引退し、山内の瑞林院に隠棲しました。
増上寺55世在禅(文化元年「祐天寺」、文化5年「寺院」参照)が8月5日、家斉に辞職を願い出て、9月10日に隠退しました。10月1日、鎌倉光明寺80世典海が台命により増上寺に住し、大僧正に任じられました。
3月、幕府は江戸の十組問屋(元禄7年「事件」参照)65組に菱垣廻船積問屋仲間として流通の独占権を与えました。その見返りとして菱垣廻船積問屋仲間は、毎年1万200両の冥加金(税金)を幕府に上納することになりました。
近年、商品の生産や流通が拡大したことに伴い、十組問屋以外の商人による商品売買が盛んになっていました。また、樽廻船の発展、海難の続発による菱垣廻船の激減により十組問屋の勢力に陰りが出始めたため、十組問屋仲間による流通独占を目指す動きが起こっていました。そこで、文化6年(1809)には杉本茂十郎を中心として三橋会所(文化6年「事件・風俗」参照)の設立を認めさせるなど、着々と手段を講じてきていたのです。
株札は1、995株に限られ、新規の加入を認めませんでした。廃業者が出た場合でも組内で適当な者に譲ることになっており、株仲間以外の営業を禁止するものでした。そのため生産者や在郷商人が反発し、多くの訴訟行動が起きました。しかし、幕府は株仲間の特権を守り、訴訟を取り上げることはなく、菱垣廻船積問屋仲間は天保12年(1841)まで存続します。
9月、松前奉行に逮捕され箱館に拘留されていたロシア軍艦長ゴローニンが釈放され、これにより2年以上にわたる「ゴローニン事件」の幕が閉じました。
文化9年(1812)、ゴローニンの安否を確認するため、部下のリコルドは大坂の海運業者高田屋嘉兵衛(寛政11年「人物」参照)を拉致しましたが(文化9年「事件・風俗」参照)、嘉兵衛はリコルドに、文化2年(1805)にロシア人が蝦夷地の日本人を襲撃した事件について、ロシア政府から釈明があればゴローニンも無事に釈放されるだろうと進言して、日本とロシアとの交渉役になることを買って出ます。1年近くをともに過ごし、嘉兵衛の人柄に絶対的な信頼を寄せていたリコルドは、嘉兵衛の申し出を受け入れ、嘉兵衛を伴って再び国後島に戻りました。文化10年5月のことです。
嘉兵衛のさまざまな助言により、松前奉行とリコルドとの交渉はとても円滑に行われました。やがて松前奉行から、ロシア人の襲撃事件はロシア政府の関知しないものであることを明記した公文書などを提出すればゴローニンを釈放する、という内容の文書が届きます。そして箱館において、ロシアからの公文書の提出が行われ、ようやくゴローニンは自由の身となることができたのです。
10月、軍艦ディアナ号に乗り込んで帰国の途に着いたゴローニンは、途中で暴風雨により危うく遭難しかけましたが、ほぼ1か月後に無事ロシアに帰り着いたということです。
『婚礼累箪笥』が刊行されました。山東京伝(天明5年「人物」参照)の作です。浄瑠璃『姻袖鏡』と累の話を付会して成った作品です。
正月より森田座で、歌舞伎『例服曽我伊達染』が上演されました。十郎、五郎、百姓金五郎、三浦荒男之助、左金吾頼兼の5役を7代目市川団十郎(享和元年「人物」参照)が演じ、女達月小夜お谷、あこや、大磯、傾城高尾、同妹かさね、政岡の6役を5代目岩井半四郎が演じました。
8月15日より市村座にて、歌舞伎『累渕糾其後』が上演されました。祐念上人と羽生村梁田與右衛門の2役を7代目市川団十郎が演じ、與右衛門女房累の役は初代尾上松緑が演じています。
「寛政の三奇人」の1人である蒲生君平は、下野国宇都宮(栃木県宇都宮市)の灯油商の家の4男として生まれました。名を秀実、通称を伊三郎と言い、君平は字です。姓は福田と言いましたが、戦国時代の武将蒲生氏郷が先祖であると聞いて、後年に蒲生と姓を改めました。
君平は14歳で、下野国鹿沼の儒学者鈴木石橋に入門。さらに黒羽藩家老の鈴木武助(為蝶軒)にも師事して、国史や古典などを学びました。また、常陸国(茨城県)を訪れ、水戸藩士の藤田幽谷などとの交流の中で、節義と憂国の学風を身に付けていきます。勤王家で、君平と同じように「寛政の三奇人」と称される高山彦九郎の存在を知ったのもこの頃でした。君平は藩士たちの話などからすっかり彦九郎に私淑し、その傾倒ぶりは寛政2年(1790)に蝦夷地見学のために北へ旅立った彦九郎を追って、自らも陸奥国(宮城県)石巻にまで赴いたほどです。しかし、折悪くも彦九郎に会うことができず、その帰路の仙台で、君平は林子平(寛政5年「人物」参照)を訪ねました。このとき君平は、子平と志を大いに語り合ったと言われ、寛政4年(1792)に刊行された君平初の著作となる『今書』は、このときの子平との対話がきっかけになったと思われます。
寛政8年(1796)、歴代天皇の墓所である山稜が荒廃していることを知った君平は、その状況を調査して書物にまとめようと志し、京に向かいました。このときの調査は旅費も乏しく、故郷に帰るのにも事欠くありさまでしたが、寛政12年(1800)に再び京を訪れた際には準備も万端に整え、前回は畿内のみだった調査を四国や佐渡にまで広げました。そして享和元年(1801)、畿内やその周辺の山稜92か所を2巻にまとめた『山稜志』(享和元年「出版・芸能」参照)の完成に漕ぎ着けたのです。このとき君平は、でき上がった原稿の序文を、上京した際の帰路に訪れた松坂の本居宣長(寛政10年「人物」参照)に送って批評を求めていますが、この年の9月に亡くなった宣長から返事が来たかどうかは不明です。
苦労の末にやっと完成した『山稜志』でしたが、山稜復興を求めた内容が尊王思想にも通じるために幕府の禁忌に触れる可能性もあり、出版をしようという版元はいませんでした。なんとか費用を工面して自費出版に漕ぎ着けたときには、原稿完成から7年もの歳月が経っていました。危惧していたとおり奉行所から呼び出しを受けた君平は、山稜復興は水戸光圀の遺志であり、それを受け継いで出版したと述べ、おとがめを受けずに済んでいます。
享和3年(1803)に江戸へ出て林述斎に学んだ君平は、江戸に定住して講義を行うことを述斎から勧められました。さっそく文化元年(1804)に駒込吉祥寺に茅屋を借りて「修静庵」と名付け、ここで講義を開きます。門人も少なく、暮らしぶりは決して裕福なものではなかったようですが、悠々自適な修静庵での生活は6年に及びました。この間に君平は『職官志』の編集や、国防を論じた『不恤緯』を書き上げています。文化6年(1809)に妻をめとりますが子をもうけることなく、文化10年に暑気あたりで寝込むと2度と起き上がることはありませんでした。享年46歳でした。何の後ろ盾もない庶民でありながら国内外の危機を訴えた君平の思想は、やがて幕末に至ると尊王攘夷思想へと発展し、勤王の志士たちに多大な影響を与えていきます。