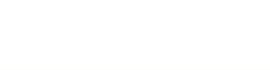

花巻(岩手県花巻市)の清水氏がこの年、自分の先祖のこととともに花巻広隆寺のことを、『広隆寺旧記』としてまとめました。広隆寺末庵如来堂は元禄年間(1688~1703)、清水氏の祖先甚兵衛が開基し寄進したものです。甚兵衛の息子の佐兵衛が親の志を継いで京都で阿弥陀如来像を造立し、江戸に船で運んで祐天上人に開眼してもらったということです。現在は勝行院にある阿弥陀三尊像がその像であるということです。
5月16日、田安家のお里久が逝去しました。祐天寺に納められた法号は清窕院瑠光芳林大姉です。その供養のため地蔵尊を造立しました。
7月15日、田安家の関係の子息が寂しました。祐天寺に葬られ、法号は応幻蓮生大童子と付けられました。
12月15日、表裏両門の下馬札の修復について、増上寺役者の添簡を添えて、寺社奉行月番大久保安芸守へ建て替えの願書を出しました。
表門の札は文字が読めなくなり、裏門のほうは柱が朽ち損じたためです。役僧祐愍が持参したところ役人松下三郎兵衛が出会い、預かりとなりました。
8月、小石川伝通院の在心が、台命により知恩院住職となりました。大僧正に任ぜられるのは、翌7年(1810)3月のことです。
在心の在任中には法然上人600回遠忌の勅会が行われたり(文化8年「寺院」参照)、青蓮院宮門跡が法然上人の勅修御伝を御覧になるためお忍びで来寺されたりしました。
文化元年(1804)頃からたびたびロシア南下の脅威を感じていた幕府は、文化5年(1808)にロシアの勢力を知るため樺太の調査を行うことにしました。この調査隊には最上徳内(天明6年「人物」参照)のほか、松前奉行配下であった松田伝十郎と間宮林蔵(文化12年「人物」参照)も加わり、この2人には特に樺太奥地の測量の役目が任ぜられたのです。
宗谷岬から樺太のシラヌシへ渡ると、ここで二手に分かれ、伝十郎は西海岸を、林蔵は東海岸を進みました。しかし、北知床岬のシャックコタンで東海岸の調査を断念した林蔵は、引き返して陸地を横断し、西海岸を進む伝十郎の一行に合流しました。それから小船で北上してラッカに到着しましたが、これ以上北進できずに一度宗谷まで引き返します。宗谷に帰着したのは文化5年閏6月で、調査出発からおよそ2か月が経っていました。
ところがそのわずか1か月後、林蔵に再調査が命じられました。今度は単身での調査で、骨まで痛み出す寒さに耐えながらの厳しいものとなりました。しかし、1回目の調査で越えられなかったラッカを過ぎ、文化6年5月に樺太最北端近くのナニオーに到達します。林蔵の目の前には波が激しく打ち寄せる大海原が広がっており、樺太が島であることが判明したのです。林蔵はさらに、交易のために大陸へ行くというアイヌ人の船に便乗し、黒竜江上流にある東韃靼のデレンに渡ると、ここにしばらく滞在して風俗などを調査したのち、9月に宗谷へ帰着しました。
林蔵の探検により初めて発見された、樺太とシベリア大陸との間の海峡は、のちにシーボルト(文政7年「人物」参照)により「間宮海峡」という名でヨーロッパに紹介され、林蔵の名は世界中に知られることになります。
2月、十組問屋(元禄7年「事件・風俗」参照)により、隅田川に架かる永代橋(元禄11年「事件・風俗」参照)・新大橋(元禄6年「事件・風俗」参照)・大川橋(安永3年「事件・風俗」参照)の架け替えや修理を請け負う三橋会所が設立されました。本来なら橋の修復は幕府が行うものですが、修復には多額な費用がかかるため、折しも文化4年(1807)に崩落した永代橋(文化4年「事件・風俗」参照)の修復費用が頭痛の種だった幕府にとって、この会所設立申し出はありがたいものだったのです。
しかし、三橋会所設立の本当の目的は橋の普請ではありませんでした。会所の発案者である江戸の定飛脚問屋・大坂屋茂兵衛は、樽廻船の就航(寛文元年「事件」参照)以来衰退していく一方だった菱垣廻船による流通を活性化させ、十組問屋を再興することがねらいだったのです。会所の頭取に任命された茂兵衛は、家業を義弟に譲って杉本茂十郎と改名し、会所取締となった町年寄樽与左衛門とともに会所の実権を握りました。問屋仲間からの出資により、菱垣廻船の船数を倍増させたり営業不振の仲間に資金を融通したりするほか、幕府へは冥加金(税金)を上納したりしたため、十組問屋は株仲間として公認され(文化10年「事件・風俗」参照)、再興がかなったかのように見えました。
ところが、会所の公金を幕府の米価調節策のための買米に使って大きな損失を出したことがきっかけで資金不足に陥り、茂十郎は問屋仲間に会所への出資を強引に行うようになります。これが仲間の反発を買い、さらに与左衛門が会所の公金を使い込んで自殺したため、文政2年(1819)に会所は廃止となりました。
式亭三馬(文化3年「人物」参照)の代表作で、この年に前編が刊行されて好評を得ました。一貫したストーリーはなく、銭湯に集う人々の会話を通して、江戸庶民の生活や世相が描かれました。
三馬自身が序文で、三笑亭可楽の落語にヒントを得たと記しているように、銭湯を舞台とした小説を書くきっかけは落語でしたが、享和2年(1802)に刊行された山東京伝(天明5年「人物」参照)の銭湯を扱った作品『賢愚湊銭湯新話』の影響を受けていることもわかっています。落語の話術を取り入れ、軽妙な筆致で江戸庶民の会話がそのまま載せられているため、『浮世風呂』は貴重な言語資料とも言えます。
この年、山東京伝作の合巻『累井筒紅葉打敷』が刊行されました。お房徳兵衛の話と綯い交ぜになっています。
また、きぬ川よえもんは洛外に住む浪人で講釈語り。お岸という美人の娘がいますが、助坊主願哲という道心者がお岸に恋慕する、というように累物に登場する人物の名前を自由に使ってさまざまな人物に仕立てています。
6月11日より森田座で、累物の歌舞伎『阿国御前化粧鏡』が上演されました。鶴屋南北(文政8年「人物」参照)の作です。尾上松助が夏狂言を一世一代とした上演です。金襖の御殿がたちまち廃屋に変わる仕掛けは大評判を取りました。また、かさね役の栄三郎が湯上がりの化粧をする様子、きれいな顔に阿国御前のしゃれこうべをつけると離れなくなり、あざになる仕掛けなど、さまざまなところに評判になるような工夫がありました。
7月26日より8月10日まで、大坂嵐座で累物の歌舞伎『草紅葉錦絹川』が上演されました。市岡和七の作です。
上田秋成は享保19年6月25日に、大坂曾根崎新地の茶屋で私生児として生まれました。名を東作と言い、和訳太郎、剪枝畸人、余斎、無腸などと号しました。父を小堀遠州の子孫にあたる旗本小堀左門とする説もありますが、秋成自身が自著『自像筥記』に「父無く其の故を知らず」と記していますので確証はありません。秋成は4歳で母に捨てられ、堂島永来町で紙や油を商う上田茂助の養子となりますが、5歳のときに天然痘を患い、一時は危篤状態になりました。このときに養父母は信心している大坂郊外の加島稲荷(現、香具波志神社)に祈り、秋成が奇跡的に一命を取りとめたことから、以後は秋成も養父母に付き添われて月ごとの参拝を怠たることはありませんでした。この出来事はのちに秋成が霊怪信仰に囚われた一因と考えられています。
幼少期の秋成は神経質で病弱ではあったものの、裕福な養父母の慈愛のもと、伸び伸びと育ち、青年期には遊蕩三昧の日々を過ごしました。しかし、父を知らず、母にも捨てられるという不幸な生い立ちと、天然痘の後遺症で右手の中指と左手の人差し指が不自由になったことが、秋成の心に深い傷を残したことは言うまでもありません。
秋成が学問に興味を持ち始めたのは20歳前後のことで、まず高井几圭に師事して俳諧を学ぶ一方、当時流行の戯作を読みふけり、和漢の古典などにも触れていたようです。宝暦10年(1760)27歳のときに農家の娘の植山たまと結婚して身を固め、翌年に養父が亡くなると嶋屋の主人となりますが、家業に専念するには至らず、明和3年(1766)には浮世草子の処女作となる『諸道聴耳世間猿』、翌4年(1767)には『世間妾形気』を刊行して作家としての一歩をしるしました。さらにその翌5年(1768)には今までとは全く趣の異なった怪異小説『雨月物語』(安永5年「出版・芸能」参照)を著し、秋成の名を不朽のものとしました。この頃からますます学問への探求心を強め、漢学を都賀庭鐘(寛延2年「人物」参照)、国学を賀茂真淵門の建部綾足、加藤宇万伎に就いて学びました。
商人として大きな成功はないものの順調に暮らしてきた秋成でしたが、明和8年(1771)に堂島の家を火災により焼失すると、加島村に移住して3年間の医学修行ののち、大坂尼ヶ崎町に医院を開業しました。技術は十分ではなかったようですが、良心的な態度で治療にあたったため患者からの信用を得て、生活は安定していきました。この間も国学の勉学に励み、真淵の『古今和歌集打聴』の校訂を行ったり、古代音韻を巡って本居宣長(寛政10年「人物」参照)と論争するなどしました。
55歳を過ぎた頃から健康を害して医者を辞め、57歳で左目を失明し、60歳を迎えると妻とともに京都に移住しました。4年後の妻の死に際しては自殺を考えるほどの打撃を受けますが、それほどに妻との生活が秋成の最も幸福な時期だったと言えます。やがて右目も患い、孤独で貧しい晩年を送ります。それでも執筆意欲が衰えることはなく、文化2年(1805)に歌文集『藤簍冊子』を刊行し、最晩年の文化5年(1808)には自らの人間観なども織り交ぜた傑作『春雨物語』を書き残しました。文化6年6月27日、門人の羽倉信美の百万遍屋敷にて76年の生涯を閉じました。