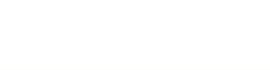

4月、本堂前用水器2個を畳講中が寄進しました。直径5尺(約167センチメートル)です。
祐全が明和年間に開白した念仏堂の常行念仏は今年まで続けてきました。しかし、毛利家からの祠堂金は前住職の代までに底を尽き、そのうえ日用の掛かりが多く借財がかさんだため、続けられなくなりました。常念仏を休みたい旨を知恩寺54世祐水に申し上げたところ、痛心のことだが仕方がないので常行は休み、三時(1日3回)の勤行供養は勤めるようにと仰せ遣わされました。
京の専念寺17世住職隆円は生涯に数多くの著作をなしましたが、その中でも特に往生伝や高僧伝の編集においては誰よりも優れていました。捨世主義(明和2年「人物」参照)を目指しましたが、師僧の許しが得られずに専念寺17世となったのが38歳のときです。以来、専念寺の経営を行いながらも、布教や著作に忙しい日々を送りました。
享和2年(1802)に初めて隆円が刊行した往生伝である『近世南紀念仏往生伝』3巻は、紀伊国で法友が集めた往生伝に、隆円が加筆して編集したものです。この本が広く人々を教化したため、隆円は八王子(東京都八王子市)大善寺で修学中のうちから編纂を始めていた『近世念仏往生伝』の刊行を決意します。全5編16巻(全15冊)から成るこの本には祐天上人の記事も含まれ、文化3年(1806)から天保元年(1830)にわたって刊行されました。
8月19日、隅田川に架かる永代橋(元禄11年「事件・風俗」参照)が深川富岡八幡宮の祭礼を見ようと集まった群衆の重みに耐えかねて崩れ落ち、多くの死傷者を出すという大惨事になりました。
永代橋は当初、幕府が管理していましたが、相次ぐ洪水や火災によって橋の修復費用がかさんだことから、幕府は享保4年(1719)に新大橋もしくは永代橋のどちらかを廃止しようとしました。これに驚いた両岸の町人たちが組合を作り、修繕などの諸経費はすべて町方で負担するということを申し出たため永代橋は残されました。修繕費用のため橋銭徴収も行われましたが、橋銭では修繕費用を賄いきれなかったため、傷んでいることを承知のうえで橋を渡らせていたのです。しかも8月15日に行われる予定だった富岡八幡宮の祭礼は、雨のために順延されていたので、待ちに待った町人たちが熱狂するのも当然の成り行きでした。
また、橋が落ちる1時間ほど前のこと、一橋家がこの祭礼の見物のため下屋敷に御座船で向かうことになり、永代橋の下を通ることになりました。そのため船が通り過ぎるまで永代橋の通行が止められていました。午前10時頃に通行が許されると、橋の西側に今か今かと待ちわびていた数万の群衆が先を争って渡り始めたのです。
橋が落ちたと叫んでも後ろの者が見えるはずもなく、押し合いながら落ちた橋桁のところまで来て初めて、あっと思うのと同時に水中に落ちていきました。それはまさしく、山東京伝の弟京山が著書『蜘蛛の糸巻』で「横へ開くべき道なき橋の上なれば、夢の様に入水したるも多かるべし」と書いているとおりのありさまでした。そのとき欄干にしがみついていた1人の武士が、機転をきかせてとっさに刀を抜き、振り回しました。けんかだと思った人がようやく後ろへ下がり、多くの人々が難を逃れました。
奉行の発表では死者の数は440人でしたが、実際には2、000~3、000人にも達したと言われ、遠く上総や房総の海岸まで流れ着いた者もありました。幕末の万延元年(1860)には河竹黙阿弥が、この永代橋崩落事件を盛り込んだ歌舞伎『八幡祭小望月賑』を書いて大当たりしたということです。
この年から文化8年(1811)にかけて刊行された、滝沢馬琴(文化2年「人物」参照)作、葛飾北斎画の本格的な長編読本です。角書に「鎮西八郎為朝外伝」とあることからもわかるように、不遇な運命をたどった弓の名手である源為朝を、空想による虚構の中で活躍させる伝奇小説です。為朝が大島に流されるまでの前編と、琉球に渡った為朝が内乱を平定する英雄として描かれる後編から成ります。
翌文化5年(1808)からは『椿説弓張月』を題材とした浄瑠璃や歌舞伎が次々と作られ、また昭和44年(1969)には三島由紀夫が戯曲化したものが上演されています。
この年、滝沢馬琴(文化2年「人物」参照)による読本『新累解脱物語』が刊行されました。累という字を分解した「田糸」姫という名の醜婦や、西入という美男などが登場します。
中村幸彦氏は「土地と人物を、前の『解脱物語』にかりた以上には、僅かの類似をしか認め難い」と述べられており、『死霊解脱物語聞書』との影響関係は薄いことがわかります。
茶道江戸千家流の祖と呼ばれる川上不白は、紀伊国新宮(和歌山県)で誕生しました。幼名を亀次郎と言い、父は和歌山藩新宮領の領主水野家に仕えていました。水野家は和歌山藩の家老という陪臣の地位にありながらも3万5、000石を領し、先祖は徳川家康の従弟にあたる由緒ある家柄です。不白は15歳で江戸に出るまで、黒潮の流れる温暖なこの土地で少年期を過ごしました。
15歳で元服ののち江戸藩邸にて仕官しますが、翌年の享保19年(1734)藩命により京の茶道表千家7代目如心斎天然に入門。如心斎は表千家流の中興の祖と言われた人物で、茶の湯の精神や技を磨く式作法「七事式」を制定したことが偉大な功績として知られます。この作法の制定に関しては不白も参画し、式の総仕上げとして如心斎とともに京の大徳寺(千利休ほか茶の湯と縁の深い寺院)に参籠するなど、重要な役割を果たしました。寛延2年(1749)に江戸へ下向した際、不白は如心斎が長い間探し求めていた利休の辞世が書かれた1軸を発見し、表千家へ戻すために所蔵者の材木問屋冬木家との交渉に力を尽くしています。不白が大徳寺の大竜和尚から「孤峯」の道号を与えられ、さらに雅号として不白を名乗るようになるのも、この頃からと言われます。
寛延3年(1750)に皆伝を得た不白は、江戸の神田駿河台に茶室黙雷庵を建立しました。大名屋敷の建ち並ぶこの地に拠点を構えたことは、不白が集めようとした門弟が武士階級を対象にしていたとも考えられます。しかし、翌年の宝暦元年(1751)に師の如心斎が逝去し、まだ幼い跡継ぎの?啄斎の養育のために京に4年ほど滞在したのちに江戸に戻った不白は、神田明神境内に茶室蓮華庵を建てました(宝暦5年「事件・風俗」参照)。神田明神は江戸庶民の鎮守・産土です。ここで主の水野家茶頭としての活動を行いつつ、武士や町人といった区別なく門人を集め、師とともに制定した七事式で茶の心を広めていったのです。そのため、不白の門下には田沼意次(安永元年「人物」参照)や島津家、毛利家などの幕閣・大名のほか、学者、能役者、医者、豪商といった多彩な顔ぶれが集まり、明和3年(1766)から1年間続けられた利休供養塔建立のための勧進茶会には、300人以上に及ぶ客人を招いたと言います。
そして、不白の才能は茶だけではありませんでした。書画の腕前は、師の如心斎が不白にだけ肖像画を描かせたと言われるほどで、茶道具も自ら作りました。俳句をよくし、俳諧の世界では俳人・不白としても評価を得ています。多芸にして多才な不白は、安永2年(1773)に55歳で茶号「宗雪」と水野家茶頭の家督を息子に譲って隠居しますが、それでもなお彼の活躍はとどまることはありませんでした。茶人の多くが禅宗であったことに対し、珍しくも熱心な法華宗信者だった不白は、『法華経』に基づく茶道哲学を大成した『不白筆記』や『茶道訓』などを著し、死の2年前まで茶会を催すなど旺盛な余生を過ごしました。89歳という長寿を全うした不白の墓は、江戸谷中の安立寺にあります。