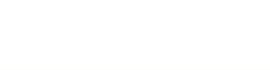

6月24日、福島県白河市大橋のたもとに水難供養祐天上人名号石塔が建立されました。阿武隈川河畔に建っており、正面に祐天上人名号、側面に「彫刻祐天大僧正六字名号立之以為 溺死一切含霊修冥福者也 文化元年歳在甲子六月廿四日」とあります。
6月17日、祐東は増上寺役者祐海に内談のうえ、寺社奉行月番水野出羽守へ願書を差し出しました。祐天寺は檀家のない寺であるため常念仏の資金がなく、継続が難しくなっているので、托鉢を許可して欲しいという内容です。
7月5日に呼び出されて参上すると、6日五つ時(午前8時)に堀田豊前守役宅内寄り合いへまかり出るよう、お達しがありました。
6日に祐東が参上したところ、ご列席のところへ召し出され、托鉢は僧侶の持ち前であるので勝手次第にいたすようにと言われ、よって願書は差し戻す旨が仰せ渡されました。
7月、東漸寺宣契は『祐天大僧正利益記』序文を書きました。
9月3日、車返本願寺(府中市)13世祐穏が寂しました。法号は安蓮社住誉上人慈仰祐穏和尚です。祐全の弟子でした。祐穏の父は青山伊勢屋長三郎と言い、祐天寺10万人講の発起人であったことがわかっています。
11月17日に祐東は、仁王の躰内に地蔵菩薩像を納めることを心願として持ち、黒田家真含院の寄進により納入しました。
米沢(山形県)阿弥陀寺に、享保2年(1717)に祐天上人が開白した常念仏の3万2、000日を供養する地蔵菩薩像が造立されました(寛政11年「祐天寺」参照)。祐天上人は江戸一本松の庵室で享保2年に常念仏の開白を勤め、それを口伝えに阿弥陀寺にて常念仏が行われたものと思われます。
寛政11年(1799)に東蝦夷地を直轄地とした幕府は(寛政11年「事件・風俗」参照)、アイヌ人を完全に幕府の支配下に置くために、積極的にアイヌ人を和人化していこうと考えました。特に、アイヌ人がロシア人からキリスト教の影響を受けることに危機感を覚え、蝦夷地に新しく寺院を建立することにしたのです。これらの寺院は、蝦夷地に流入した開拓民たちの葬儀を執り行い、墓所となる役目も担いました。
この年に建立されたのは、浄土宗善光寺、天台宗等澍院、臨済宗国泰寺の3か寺で、善光寺は有珠に置かれて山越内から白老まで、等澍院は様似に置かれて勇払から襟裳まで、国泰寺は厚岸にあって十勝から千島までを、それぞれ教化区域とされました。檀家がないため、寺領として年に米100俵、手当金20両3人扶持という身分が与えられましたが、赴任してきたそれぞれの寺院の住職は10年の任期が終えるのを待たずに遷化したり、病気による隠退が相次いだそうです。
長寛政元年(1789)に恋川春町(寛政元年「人物」参照)の『鸚鵡返文武二道』が絶版となり、寛政3年(1791)には山東京伝が手鎖50日、版元の蔦屋重三郎が財産の半分を没収されるなど(寛政3年「事件・風俗」参照)、幕府の出版統制は年々厳しくなっていました。
この年の5月には「太閤記」を題材としたものが次々と絶版に追い込まれ、喜多川歌麿(享和3年「人物」参照)も『太閤洛東五妻遊観』の挿絵を描いたことで入牢3日、手鎖50日の刑に処されました。「太閤記」は太閤の名が示すとおり豊臣秀吉の栄華を描いたものでしたが、江戸幕府の草創期の記事を多く含むため、幕府としては家康に論議が及ぶことを危ぶみました。また、歌麿の絵は愛妾をはべらす太閤の姿が11代将軍家斉(天明7年「人物」参照)を揶揄しているとして絶版を命じられ、版木も没収されたのでした。
さらに同年、十返舎一九(享和2年「人物」参照)も『化物太平記』を著して手鎖50日の刑に処せられました。書名の「太平記」とは「太閤記」を指し、内容は秀吉をヘビに、織田信長をナメクジにたとえたもので、作品は絶版、版元も罰金を科せられています。
10月、紀伊国那賀郡(和歌山県那賀郡)の医師、華岡青洲(「人物」参照)により、全身麻酔を使った乳がんの手術が成功しました。このときの患者は大和国(奈良県)に住む60歳になる女性で、青洲の前にも数人の医者に診てもらっていましたが、当時乳がんは不治の病であったため、どの医者からも匙を投げられていました。それまでの外科手術は、外傷を縫合したり腫瘍を切開したりするだけでしたので、腫瘍を摘出した青洲の手術は、世界でも類を見ないものだったのです。
また、手術の際に使われた麻酔薬は通仙散と言い、青洲が試行錯誤の末に開発したものです。中国の三国時代(220~280年)の医者が麻酔として使っていたという伝説のある曼陀羅華(チョウセンアサガオ)を主成分としていますが、この花には毒性があり、誤って食べるとけいれんや呼吸困難などを引き起こします。この毒性を抑えつつも最大限に麻酔効果を得られる調合を知るため、開発の最終段階で、青洲の妻が自ら実験台となり失明してしまうという事件もありました。
青洲はこののちも多くの乳がん摘出手術を行うほか、関節離断や尿路結石の摘出手術なども成功を収め、華岡流外科手術は諸国に知られていきました。
12月、山東京伝(天明5年「人物」参照)著『近世奇跡考』が刊行されました。市井の風俗、史跡についての逸話などを考証して記した書物です。累の故郷、羽生村についての記事があります。
7月に河原崎座で、歌舞伎『天竺徳兵衛韓噺』が初演されました。初代尾上松助が出演し、水中の早変わりを見せて大評判となりました。のちにこの作品はその息子の3代目尾上菊五郎に継承され、音羽屋の家の狂言となりました。再演を重ねるたびに改訂され、文化6年(1809)に『阿国御前化粧鏡』と改題増補された際には、4世鶴屋南北が「湯上がりの累」の趣向を取り入れて評判になりました。
「医聖」と賞される華岡青洲は、名を震、俗名を雲平と言い、紀伊国那賀郡平山(和歌山県那賀郡那賀町平山)にある小さな山あいの村で誕生しました。家は祖父の代から医業を営んでいたことから、青洲は子どもの頃から父に医術を学び、成長するにつれ京へ出て最先端の医術を学ぶことを望むようになります。家計は決して裕福ではありませんでしたが、その熱意に押された父はなんとか工面をして青洲の希望をかなえました。青洲23歳のときのことです。
京へ出た青洲は、古医方の権威である吉益南涯と、オランダ流外科医として一家をなしていた大和見立のもとで医学を学びました。「医者となるからには、治療の技は最高を究めなくてはならない」という信念を抱き、中国・三国時代(220~280年)の医者の華陀に憧れて、誰も治療ができないような難病を治せる医者になりたいと友人たちに話していたそうです。華陀は曼陀羅華(チョウセンアサガオ)を調合した麻酔薬を使って、神業的な外科手術をいく度となく成功させた名医と伝えられている人物でした。青洲は寝食を忘れて勉学に励み、医学書だけでなくさまざまな種類の本を読破し、優れた技術を持った医者がいると聞くと必ずそこへ出向いて技を身に付けたと言います。
やがて3年間の遊学を終えて故郷へ帰ると、それを待ちかねたかのように父が死去。家業を継いだ青洲は日々の診療の合間を縫って遠近の山谷で薬草を蒐集し、日本の華陀となるべく研究を続けました。特に青洲が力を注いだのが大手術をするには欠かせない麻酔薬の開発で、目標とする華陀も使用した曼陀羅華に注目しました。しかし曼陀羅華は毒性が強く、調合の具合によってどのような効果や副作用があるのかがわかりませんでした。動物実験だけでは、人間に対しての効果はわかりません。悩む青洲に母於継と妻加恵が、実験台になることを申し出ました。青洲はためらい断りますが、わが子、わが夫のため、そして世の中の難病を抱える人々のためにと、2人は自らを顧みずにたびたび薬を試用したと言います。これにより母は死去、妻は失明に至りますが、尊い犠牲により完成された麻酔薬「通仙散」は、世界初と言われる全身麻酔による乳がん摘出手術を成功させたのです(「事件・風俗」参照)。
不治の病だった乳がんを治療した青洲の名は人々に知れ渡り、診療所には大勢の患者だけでなく、その教えを受けようと全国から門下生も集まるようになりました。やがて家塾兼診療所として春林軒を設立し、ここで青洲は「内外合一・活物窮理」の思想のもとに、弟子たちを指導していきました。これは内科や外科、漢方や蘭方の区別なく、個々の患者の性質や病気の特性に適応した医療を目指すことです。和歌山藩から侍医としての招きもありましたが、診療所と藩医の掛け持ちという特例を得て、生涯僻村に身を置いて民衆の治療に力を注ぎました。青洲の教えを受け継いだ門下生は1、000人を超え、多くの名医が誕生しました。天保6年10月、76歳でこの世を去った青洲の偉業は、昭和29年(1954)には世界外科医学会にも認められ、アメリカにある世界外科学会栄誉会館内の日本室には、青洲の書や刀剣などが飾られています。