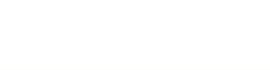

6月3日、竹姫の局であった芳川が逝去しました。法号は見珠院殿性誉嘉延法尼です。祐天寺過去帳には「芝御守殿若年寄芳川コト」とあります。本性院殿(享保18年「祐天寺」参照)、栴林院殿(寛政3年「祐天寺」参照)とともに合葬された墓石が祐天寺墓地に現存しています。
在禅は、祐天寺で建立された瑞泰院常念仏堂の本尊阿弥陀如来像の開眼供養の際、開眼供養疏の文章を代作した僧で(明和6年「祐天寺」参照)、文化5年(1808)には増上寺55世住職となっています。この当時の在禅は、増上寺学寮の寮主でした。
正月に在禅が講義した『称讃浄土教疏』の「称讃浄土教」とは、玄奘三蔵が訳した『仏説阿弥陀経』のことです。この本についてのいわば解説書のようなものを『称讃浄土教疏』と言いました。『称讃浄土教疏』という本が当時は何冊かあり、在禅はおそらくそれらの本についての講義を行ったものと思われます。
4月13日、家治は日光東照宮へ参詣に出発しました。将軍による日光社参は8代将軍吉宗が享保13年(1728)に参詣してから(享保13年「事件・風俗」参照)、実に48年振りのことです。社参の布告は明和5年(1768)に出ていましたが、準備の遅れや、家治の正室五十宮(心観院殿)の逝去(明和8年「祐天寺」参照)などがあったため、この年まで延期されてしまったのです。
江戸を発った家治一行は、途中岩槻城や古河城、宇都宮城を経て、16日の酉の刻が過ぎる頃(午後7時頃)に日光山に到着。翌日、束帯姿に改めた家治は東照宮のほかに初代家康、3代家光の廟墓にも参詣しました。
家治は18日には山を下り、江戸城へ帰り着くのは20日のことで、延べ400万人余、馬は30万頭余がこの社参に動員されたと言われます。費用はおよそ22万両もかかったそうですが、社参の行列が通る街道筋の住民たちに課せられた助郷などの負担も含めると、経費はさらに莫大であったと思われます。
代々将軍の奥医者を勤める桂川家の4代目桂川甫周国瑞(安永6年「人物」参照)と、オランダ商館付きの医者であり植物学者のスウェーデン人ツュンベリーの出会いは、日本橋本石町のオランダ人定宿長崎屋でのことでした。オランダ商館長フェイトが将軍拝謁のために江戸へ参府してきた4月、甫周が商館長に随行してきたツュンベリーを訪ねてきたのです。甫周とともに『解体新書』(安永3年「出版・芸能」参照)の翻訳に努めた中川淳庵も一緒でした。ツュンベリーの江戸滞在中、2人は毎日長崎屋を訪れて、熱心に教えを求めました。頭の回転が速くはつらつとした甫周と上手なオランダ語を話す淳庵に、ツュンベリーは今までの訪問者たちにはない知性を感じ、3人は親交を深め、さまざまな知識を交換し合いました。ツュンベリーは甫周と淳庵から生植物や鉱物を、2人の日本人はツュンベリーから外科用器具を譲り受け、さらに医学を学んだという受講証明書のようなものも受けました。このとき得た知識と技術により、甫周はこの頃全国的に流行した麻疹の治療に努め、その功績をもって奥医者に昇格しています。
オランダに帰国したツュンベリーは、のちに『日本紀行』という著書の中で甫周について書き、やがて甫周の名はロシアにまで知れ渡ることになるのでした。
上田秋成(文化6年「人物」参照)による怪異小説『雨月物語』が刊行されました。保元の乱で敗れた崇徳院の御霊を西行が一夜供養する「白峯」、荒れ果てた村で亡霊となっても夫の帰り待つ「浅茅が宿」、親子が高野山で豊臣秀次の亡霊に会う「仏法僧」、嫉妬に狂った女の亡霊に取り殺される「吉備津の釜」、蛇に魅入られた男が道成寺の法海和尚に助けられる「蛇性の婬」など9話の短編からなります。
秋成は『剪灯新話』『警世通言』などの中国小説と、日本の古典文学である『万葉集』『源氏物語』『保元物語』『古今著聞集』、謡曲「砧」「道成寺」などを巧みに組み合わせ、人間の執念や執着、悲しみ、怒りなどを表現しました。わが国における怪異小説の最高傑作と言えます。
池大雅は京都の町人菱屋嘉左衛門の子として生まれました。父とは4歳のときに死別しますが、教育熱心な母の影響で「3歳で文字を知り、5歳で書を善した」と伝えられます。また7歳のときには黄檗山万福寺で書を披露したことがあり、その神童ぶりを絶賛する中国僧の七言律詩も残されているほどです。
15歳になった元文2年(1737)には父の菱屋嘉左衛門の名を襲名し、扇屋を開店しました。大雅は幼い頃から絵にも親しんでいたようで、一説には土佐光芳に学んだと言われますが、扇絵は土佐派や琳派の流れにはよらず『八種画譜』という中国風の絵を描きました。のちには南画を大成させた大雅ですが、扇絵はいっこうに売れず、大雅20歳の寛保2年(1742)には住居を聖護院村に移しました。この間に生涯の友となる篆刻家の高芙蓉や書家の韓天寿とも出会い、大雅は良き師友に恵まれて新進の文人画家としての活動を始めることになりました。大雅の初期の作品の1つに友の送別のために描いた「渭城柳色図」がありますが、この絵は淡彩で描かれた中国画で、大雅の若さ特有の繊細さがよく表れています。
延享3年(1746)に、のちに玉瀾と号す由可(または町)と結婚しました。玉瀾は大雅に絵を学び、大雅の作風をよく真似て描いていたようです。元来おおらかな性格の大雅には、さまざまな逸話が残されているのですが、玉瀾にまつわる話も少なくありません。あるとき、大雅が筆を忘れて家を出たことに気付いた玉瀾が、あとを追って筆を渡すと、大雅は「いづこの人ぞ、よく拾い給はりし」と言って別れました。またこのとき玉瀾も何も言わずに家に帰ったそうです。大雅は物事に熱中するあまり周りが見えなくなることがたびたびあり、そのへんのことは玉瀾もよく心得ていたようです。
大雅の作風が完成するのは40代に入ってからで、水墨、金碧、指墨、点描など多彩な手法を駆使して障壁画や屏風絵といった大きなものから、画帖や扇のような小さなものまで、おびただしい数の作品を残しました。代表作としては高野山遍照光院や万福寺の障壁画、「西湖春景・銭塘観潮図」「柳下童子図」などの屏風画があります。また、画帖としては明和8年(1771)の49歳のときの作品「十便十宜帖」があります。この作品は与謝蕪村(天明3年「人物」参照)との合作で、世俗を離れた伸びやかな画風が特徴です。
大雅は安永5年(1776)4月13日に54歳で亡くなりますが、大雅を慕う門人たちによって、菩提寺の京都浄光寺には供養の香華が絶えることはなかったそうです。天明4年(1784)に玉瀾が没してまもなく、京都双林寺の境内に大雅堂が建てられ、大雅の偉業を永く後世に伝えました。