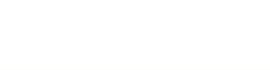

魚津大泉寺で祐天上人筆と言い伝えられてきた名号軸(布に六字名号の書かれたもの。嘉永6年「祐天寺」参照)を表装しました。
龍の額が神田住人欣誉貞源により制作されました。裏に祐全の名号が大きく書かれています。現在は箱根塔之沢環翠楼に保存されています。貞源の法号と見られる「欣誉貞源禅門」(安永6年7月4日寂)が祐天寺過去帳に載っています。
この年の8月、東西本願寺は自宗を「浄土真宗」と公称することを寺社奉行に申し出ました。本願寺の宗名は一向宗・本願寺宗・無碍光宗などと呼ばれ、統一性がないからというのが理由です。本願寺は、浄土真宗という呼び方は親鸞上人が『教行信証』という書物の中で示したのが始まりだと主張しました。しかし、この件に関して幕府から意見を求められた増上寺は、「浄土真宗」の呼び名は、すでに善導大師(613~681)の『観経疏』に見られると反論します。そして、法然上人建立の浄土宗を浄土真宗と称するとあるのだから、「浄土真宗」とは浄土宗のことを指すと主張し、本願寺の申し出は認められないと答えました。この増上寺の意見により本願寺の宗名を一向宗と呼ぶこととなりましたが、本願寺は猛反発します。以後本願寺と増上寺は寛政元年(1789)に一応の決着が付くまでの15年間にわたり、「浄土真宗」の呼び名を使用するのはどちらが正当かという論争を繰り広げることになったのです。
本願寺が宗名を「浄土真宗」と公称することが認められるのは、約100年後の明治5年(1872)のことになります。
10月、隅田川に浅草と本所を結ぶ、長さ84間(約150メートル)の新しい橋が架設されました。橋の名前は大川橋(現、吾妻橋)です。
大川橋の下流にある両国橋までは約2キロメートルあり、その間に3つの渡し場がありましたが、隅田川は水量が多くて危険なうえ、災害時には船も止まってしまい、周辺の住民たちは大変不便な思いをしていました。特に火事のときには避難できなくなってしまうので、橋の架設が強く望まれていたのです。しかし幕府は、上流に橋を造るとそれが洪水などで崩壊した場合、その材木で下流の両国橋が壊れることを恐れて、なかなか架設の許可を出しませんでした。
そこで安永2年(1773)、浅草花川戸町の伊右衛門と下谷龍泉寺町の源八が、橋の建設費用はすべて民費で賄い、武士以外の通行者から一律銭2文ずつを徴収して橋の維持費とすること、6年後には冥加金50両を納めることなどを記した願書を幕府に提出しました。さらに、大川橋が壊れて下流の橋に損害を与えた場合は、損害額500両に対してはその3分の2、1、000両までに対しては2分1を弁済することを約束し、ようやく架設の許可が下りました。
大川橋を当時の人々は俗に吾妻橋と呼んでいました。そのため江戸後期になると吾妻橋の呼称が定着し、明治時代に正式名となりました。
西洋の解剖学を日本に初めて伝えた『解体新書』が刊行されました。ドイツ人クルムスの『ターヘル・アナトミア』のオランダ語版を、杉田玄白(明和8年「人物」参照)・中川淳庵・石川玄常・桂川甫周(安永6年「人物」参照)らが協力して翻訳したものです。翻訳者として名前は記されていませんが、前野良沢(安永3年「人物」参照)も翻訳にかかわっていることは確かで、唯一オランダ語の知識を持っていた良沢が指導的立場にあったことは言うまでもありません。
翻訳のきっかけは、明和8年(1771)に小塚原の刑場での腑分け(解剖)を実見したこと(明和8年「事件・風俗」参照)でした。このとき、玄白たちはいかに人体の内部について無知であったかを痛感し、『ターヘル・アナトミア』の翻訳を決意したのです。
さっそく翌日から築地の中津藩邸内の良沢宅に集まり、翻訳が開始されました。しかし、満足な辞書もなく翻訳は困難を極めました。翻訳に着手してから刊行されるまでの4年間、オランダ商館長に教えを受けたりしながら、彼らは11回も原稿を書き改めています。
このような玄白らの努力により刊行された『解体新書』は、中国伝来の漢方医学しか知らなかった当時の医者のみならず、一般の人々にも驚きを与えました。しかし、『解体新書』の内容はかなり簡略化され、あいまいな部分が多いのも事実です。また、訳文は漢文で書かれ、注釈が翻訳されていないなどの不備もありました。のちに玄白は高弟の大槻玄沢に改訂を依頼し、『重訂解体新書』が刊行されたのは文政9年(1826)のことでした。
4月に中村座で、歌舞伎『御誂染曽我雛形』が初演されました。その中には、のちに歌舞伎十八番の1つとなる『鎌髭』が含まれています。六部(巡礼のような姿で物乞いをする者)の本性を見破った下男が、ひげ剃りの折に鎌で首を掻こうとするが果たせず、にらみ合うという話です。
8月3日より森田座で、歌舞伎『累二世月波』が初演されました。与右衛門女房かさねの役は初代中村富十郎が演じました。片足に下駄を履いてタテ(立ち回り)を工夫した点が賞賛されました。
前野良沢は名を熹、号を蘭化と言い、通称、良沢と呼ばれました。医学史上の画期的解剖学書『解体新書』(「出版・芸能」参照)の序文に、杉田玄白(明和8年「人物」参照)とともに翻訳の功労者として賞されていますが、その業績はあまり知られていません。
良沢は幼少時に両親を亡くしたため、多感な少年時代を伯父の山城国(京都府)淀藩医宮田全沢からさまざまな影響を受けて育ちました。良沢が蘭学の道を志ざすようになったのも、「人のしないことをせよ」という伯父の教えがあったからだとも言われています。また、豊前国(大分県)中津藩医の前野東元の養子となって藩主に仕えるようになってからは、同僚にオランダ語を見せてもらったことがきっかけでオランダ語に興味を持ち始め、40歳を過ぎた頃に青木昆陽(享保20年「人物」参照)からオランダ語を学びました。そして、オランダ商館長が江戸へ参府したときには、杉田玄白とともにオランダ語通訳を訪ねてオランダ語を教えてもらおうともします。しかし、通訳からは「オランダ語は江戸にいながら学べるほど簡単なものではない」と断られてしまいました。2人ともこの意見はもっともだと思いましたが、このとき、玄白はあえて学ぼうとは思わなくなったのに対し、良沢はますます学習意欲に燃え、独学でオランダ語を習得していこうと考えました。
そして明和7年(1770)、長崎に遊学することができた良沢は、オランダ語通訳のもとでオランダ語の研鑽を積み、ここで『ターヘル・アナトミア』を購入します。これがのちの『解体新書』でした。明和8年(1771)の千住骨ヶ原(小塚原)での腑分け見分(明和8年「事件・風俗」参照)の際には玄白も同じ本を持ち寄り、実物の臓腑の位置と同書の図とが全く同じであることに感嘆して『ターヘル・アナトミア』の翻訳を誓った彼らでしたが、翻訳作業を進めるうち、玄白と良沢との間には少しずつ意見の違いが出てきます。一刻も早く『解体新書』を世に送り出したいとする玄白に対し、良沢は時間がかかっても完全を期すべきだと主張しました。『解体新書』翻訳編集のメンバーには有能な蘭学者たちがそろっていましたが、オランダ語を使いこなせたのは良沢ただ1人で、それだけに良沢は正確で完全なものを目指したのでしょう。そして、結局『解体新書』に良沢の名前が訳者として載ることはありませんでした。この本には不完全なところが多かったため、良沢が自分の名を出すのを辞退したからだと言われています。
『解体新書』刊行後は玄白とも疎遠になった良沢は、医学だけでなく歴史や地理などのオランダ語で書かれた本の翻訳に打ち込み、生前は出版されることはなかったものの、写本されたものが世の中に広まりました。当時の良沢の名声は非常に高く、偏屈で孤高を愛すという性格ながらも中津藩主からは多くの扶助を受け、最上徳内(天明6年「人物」参照)や高山彦九郎などとも交友がありました。また、門人に宛てた手紙からも情の厚さがうかがわれ、晩年に至っても学問の情熱が失われることはなかったと言います。享年81歳でこの世を去った良沢は、上野(現在は杉並区梅里)慶安寺に葬られました。