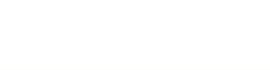

正月12日、祐全は下馬札の願書を松平和泉守へ出しました。また、3月26日には、釣鐘の表にある「御紋 文昭院殿御追福 近衛禅閣基俵公姫君大夫人一位尊尼御寄付」という文を写し、下馬札を願う正当性をさらに強調した願書を提出しました(宝暦11・12年、明和元・2・3・4年「祐天寺」参照)。
1月22日、大坂源正寺の祐説が示寂しました。祐説は祐海のもとで修行した人物です(宝暦11年「祐天寺」・「説明」参照)。
3月、神奈川県大井町に、祐天名号の付いた廻国供養塔が建立されました。正面には「廻国供養塔(梵字)南無阿弥陀佛 願主知足善了 金子村」右側面には「宝暦十三癸年三月吉日助力人足三百人」と刻してあります。
4月、群馬県富岡市の星田虚空蔵山に祐天上人名号石塔が建立されました。廻国巡礼者であった妙善法尼が、虚空蔵山に納経した証として建立されたと見られます。
三種宝物とは、祐天上人の遺骨舎利と、歯骨(享保3年「祐天上人」、延享4年「祐天寺」参照)、それに舌根(荼毘に付したときに焼け残ったと言う。享保3年「祐天上人」参照)のことです。これら3種の宝物を納める厨子と、その厨子を覆う袱紗が、竹姫により寛延元年(1748)に寄付されました。宝暦13年の6月となり、厨子および紫の紋付きの袱紗も修復がやはり竹姫により行われました。その際はお附きの御徒蓮が諸事お世話係でした。
この頃、関宿大龍寺に逆さ名号塔が建立されました。祐天上人の名号が、左右逆に陽刻されており、墨を塗れば簡単に紙に写せる仕組みになっています。12基刻されている法号のうち一番年代の遅いものに宝暦12年と記されているため、この頃に石塔は建立されたと思われます。
9月(『華頂要略』では11月)、伝通院31世の澤真が知恩院54世住職となりました。澤真は、本所霊山寺、飯沼弘経寺などを歴住し、このとき75歳でした。同年11月21日には大僧正となりましたが、明和2年(1765)7月には遷化しました。在任中には、天樹院(初代将軍徳川家康孫の千姫)100回忌の不断念仏を修しています。
それまでは茶と言えばほとんどが抹茶を指しました。蒸して乾燥させ、茶臼で挽いて粉末状にした抹茶を点てる礼儀作法は、その茶道具や茶室の装飾と相まって、「茶の湯」と呼ばれて主に貴族の間で風雅な遊びとしてもてはやされ、やがて16世紀後半頃、茶聖・千利休により大成されました。
煎茶の喫茶方法は、中国明・清代に考案されたもので、日本へは黄檗宗宗祖隠元隆琦(寛文3年「人物」参照)により伝えられたと言われています。隠元が後水尾法皇から帰依を受けたこともあり、最初は貴族などの上流階級の人々に親しまれていました。しかし享保16年(1731)、売茶翁(「人物」参照)と呼ばれる黄檗僧が京の東山で通仙亭という名の茶店を出したことから、煎茶が一般的に普及するようになっていきました。さらに、京の宇治に住んでいた永谷宗七郎(宗円)が、それまでの「黒製」と呼ばれる煎茶の製法に代わり、「青製」という製法を編み出します。これは、黒製の製法の途中で茶葉を揉む工程を加え、これにより今までにない香りと味を引き出すことができたのです。煎茶はこの新製法の開発で、さらに大変な人気を呼びました。
本居宣長(寛政10年「人物」参照)は松坂(三重県松阪市)で小児科医院を開業し、医療に携わるかたわら、国学の研究を続けていました。やがて、賀茂真淵(延享3年「人物」参照)の書いた『冠辞考』(宝暦7年「出版・芸能」参照)を読み、深い感銘を受けた宣長は、ぜひ真淵に会いたいと願うようになっていました。
一方、真淵はこの年、村田春郷・春海(文化8年「人物」参照)兄弟を連れて伊勢・大和を巡る旅に出ていました。松坂にも数日滞在していましたが、宣長がそのことを知ったのはすでに真淵たちが旅立ったあとでした。諦めきれなかった宣長は、真淵の帰途を待ち受けて、5月25日の夜に旅籠新上屋の一室で対面することができました。このとき、宣長34歳、真淵68歳でした。宣長の日記には「25日、岡部衛士(真淵のこと)当所新上屋一泊始対面」と実に簡略に記されているのみですが、2人は『古事記』について話し合い、真淵が宣長に『古事記』研究を託したとも伝えられています。
国文学者・佐々木信綱の名文「松坂の一夜」によって世に知られるようになった2人の出会いですが、宣長が真淵に会えたのはこの一度きりで、以後は手紙のやり取りで教えを受けました。しかし、この出会いは宣長の生涯を決定したのです。翌年から宣長の『古事記』研究は確実なものとなり、大著『古事記伝』(文政5年「出版・芸能」参照)の完成へと向かいます。
この年、深井志道軒をモデルとした小説が刊行されました。作者は平賀源内(宝暦7年「人物」参照)です。
志道軒は浅草寺の境内に小屋を設け、談義を行っていた僧です。初めは軍談などをしていたようですが、おどけた口ぶりで人々を笑わせ、世の中の悪口を平気で言うのが評判となり、「いま江戸で有名なのは市川海老蔵と志道軒だ」とまで言われる人気者でした。
とは言うものの、全5巻からなるこの本は、志道軒の伝記としてはいい加減なもので、志道軒を主人公に借り、『ガリバー旅行記』を思わせるような「大人国」「小人国」などの架空の世界から、「北京」「はるしや」「ぺぐう」「天竺」「おらんだ」といった世界諸国を遍歴させ、世の中を痛烈に批判したものでした。
日本にとどまらず世界を遍歴させ、ありとあらゆる経験を積ませて初めて世の中を批判させたのは、世の中を知ろうともせず机上の空論ばかりだった識者たちに対する批判でもありました。
のちに『風流志道軒伝』は談義本に遍歴物の流行を促すことになります。
日本における煎茶道の始祖と言われる売茶翁は、肥前国蓮池(佐賀県佐賀市)に生まれました。幼名は菊泉と言います。父は蓮池藩主鍋島家の医師でしたが、売茶翁が9歳のときに亡くなりました。11歳で黄檗宗龍津寺の化霖道龍のもとで出家し、このときに名を元昭、号を月海と改めました。師の化霖は黄檗宗本山万福寺の独湛性瑩の法を嗣いでおり、独湛は黄檗宗宗祖の隠元隆琦(寛文3年「人物」参照)の弟子です。隠元は日本に初めて煎茶を伝えた人物と言われており、万福寺には煎茶の文化が濃く伝わっていたと思われます。売茶翁は出家後まもなく万福寺で独湛に会い、優秀さを讃えられて特別に偈をたまわっているので、このときすでに煎茶に触れていたとも考えられます。
求道心が人一倍強かった売茶翁は、22歳になったとき病にかかりますが、これは修行が足りないためと奮起し、諸国行脚に出ることを思い立ちます。江戸から極寒の東北へ旅し、あるいは筑前の山中で麦の粉と谷の水だけでひと夏を座禅して過ごすなどの苦行も積みました。行脚は足掛け10余年に及び、この修行中に、長崎で中国人に煎茶の作法を教わったとも言われています。
故郷の龍津寺へ戻ったとき売茶翁は33歳になっていました。それからの数十年間は、ただひたすら寺務をつかさどる日々を送りますが、57歳の頃、すべてを弟弟子に預けて寺を出てしまいます。それから数年後、売茶翁は京の東山で通仙亭という茶店を出したのです。店先には「茶銭は黄金百鎰より半文銭までは、くれ次第、ただのみも勝手、ただよりはまけもうさず」と掲げ、自分を「おちぶれたおやじ」と称しました。当時、茶を売るという行為は賤しいものとされていましたので、客の中には売茶翁を破戒僧だと非難する人もいました。しかし売茶翁は気にせず、この身がどんな俗界にあっても、要は心であり、寺院でなくても悟り修行する道は無限にあると言ったそうです。売茶翁の出した茶店により煎茶は一般的なものとなり、煎茶を味わいながら清談を楽しむことが文人たちの間で流行し始めました。
さらに売茶翁自身の、俗にあっても俗に染まらずという清々しい精神性も影響したのでしょう。売茶翁の周りには儒学者、医者、僧侶、画家、歌人など、多彩な文人たちが集うようになりました。その中には、池大雅(安永5年「人物」参照)や上田秋成(文化6年「人物」参照)、木村蒹葭堂(宝暦12年「人物」参照)、与謝蕪村(天明3年「人物」参照)など、この時代を代表する人々もいました。「売茶翁」と敬意を込めて彼が呼ばれるようになったのは、この頃からと思われます。また、還俗して名を高遊外と改めた寛保2年(1742)には、現在に通じる緑茶の創始者である永谷宗円(「事件・風俗」参照)と会い、今までにない煎茶の味を賞嘆しています。
売茶翁の売茶生活は宝暦5年(1755)81歳で幕を閉じました。体力の限界を感じてのことです。彼がこの世を去るのはそれから8年後のことで、遺体は遺言により火葬後に遺骨を粉にして川に流されたと言います。