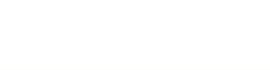

2月に閻魔王坐像を、4月8日に奪衣婆坐像を造りました。
9月18日、祐天寺第3世祐益がいとまの許しなく退寺しました(宝暦12年「祐天寺」参照)。その退寺の理由は定かでありません。延享3年(1746)住職就任以来、足掛け7年間の在住期間でした。
後継の第4世住職には故檀的(元文元年「祐天寺」参照)の弟子、檀栄が選ばれました(宝暦3年「祐天寺」・宝暦10年「新妻家略系図」参照)。檀栄はいわき出身で祐天上人の妹の血縁にあたる人物です。
9月19日五つ半時(午前9時頃)、吹上御殿浜岡より急用の手紙が来ました。風邪気味であった月光院(享保5年「人物」参照)がこの2、3日は格別気分が優れないので、ご機嫌伺いを勧める内容でした。早速隠居祐海はご機嫌伺いに参上しました。20日暁六つ時(午前6時頃)に祐海がご機嫌伺いの手紙を出すと、同日九つ時(正午頃)過ぎに月光院逝去の悲報がもたらされました。享年68歳でした。
月光院は増上寺に葬られることになりましたが、祐海は年来厚い恩顧をこうむっていることを申し述べ、葬送の際に棺近くお供をしたい旨と法事の際に祐天寺が納経拝礼をつかまつりたい旨を年寄たちに願い出ました。また、月光院の念持仏を祐天寺でお祀りしていることを述べ、位牌もお祀りして永くご回向したいと内々に願いました。位牌は許可され、お供の件などについては増上寺に願い出て許可されました。
月光院の葬送は10月3日に行われ、6日に増上寺で法要が執り行われました。
11月1日、月光院の仮位牌が祐天寺に納められました(文政12年「祐天寺」参照)。法号は月光院殿従三位理誉清玉智天大禅定尼です。仮位牌は白木の板札を蓮座に貼り付けたもので、月光院中陰の間吹上御殿に安置され、この日松本伊太夫のお供で祐天寺に奉納されました。
11月3日、若年寄松平宮内少輔より渡された書付を持って、月光院附き用人渥美伊勢守が祐天寺に来寺しました。書付には月光院仮位牌を納めるにつき100両を寄進するので、忌日年忌の回向を行うようにとの仰せ渡しがありました。
10月26日、檀栄は寺社奉行青山因幡守へ召され、書付をもって仰せ渡しがありました。月光院がご逝去の節、祐天寺の千部執行は例年どおり許可するようにと仰せおかれたとのことでした(宝暦5年「祐天寺」参照)。
また、11月3日、月光院附き用人渥美伊勢守が祐天寺に来た折(前項参照)、「千部執行については委細を寺社奉行に申し付けておく」旨の若年寄松平宮内少輔よりの書付を渡されました。
日蓮宗大本山の長栄山本門寺は、宗祖日蓮が入寂した聖地とされ、直弟の日朗によって創建された寺院です。本門寺第12世日惺が徳川家康と親交があったため、本門寺は徳川家や諸侯の菩提寺あるいは祈願所として、堂塔や什物の寄進を受けました。
本門寺の五重塔は、日惺に帰依していた2代将軍秀忠の乳母が秀忠の疱瘡快癒の祈願を本門寺に依頼し、のちに疱瘡が治ったことにより慶長13年(1608)に建立寄進されたものです。宝暦2年に幕府は、この五重塔の破損がひどくなってきたために本門寺へ銀100枚を与え、修復を申し付けました。修復工事は翌3年(1753)に終了します。
6月20日、上野不忍池の土手からすべての茶屋が引き払われました。ここで言う茶屋とはいわゆる妓楼のことで、多くの遊女を抱え風紀を乱しているという理由からでした。
幕府は延宝6年(1678)にも茶屋女への制限令(延宝6年「風俗」参照)を出し、その後も何度か禁令を出していますが、効果はありませんでした。そのため、この頃の不忍池の土手には60軒近くの茶屋が並び、そこで働く遊女たちは360人にも及んだと言います。また、これらの茶屋は生活排水を不忍池に捨てたため、水が汚れて魚が死んでしまうなどの被害も出しました。しかし、この水質汚染は土手から茶屋が引き払われると、元に戻ったということです。
それにしても、360人もの茶屋女たちはどこへ行ったのでしょうか。次の句は当時流行した落首です。
忍ばずにはれて住むぞと思ひしに
いづくへなりといけの端とは
熊本藩は54万石という大きな藩でしたが、その財政は大変厳しいものでした。参勤交代や江戸藩邸における費用などにも事欠くありさまで、商人たちからは「借金の踏倒しでは諸藩中第一」と言われるほど、その内情は火の車だったのです。こういった状況の中で、6代藩主となった細川重賢(宝暦6年「人物」参照)は宝暦2年、藩政改革に挑みます。これが宝暦改革です。
まず重賢は、中級藩士であった堀平太左衛門勝名を大奉行に抜擢することから始めます。重臣たちの反発を受けつつも、平太左衛門はその手腕を発揮し、徹底した節約により藩の支出を抑えることに成功しました。また何よりも、身分が低い者であっても手柄を立てた者は昇進させるという重賢の姿勢が藩内を活気付かせました。
さらに重賢は平太左衛門に中国の刑法を学ばせ、『刑法草書』を作らせました。この刑法では、それまで死刑と追放刑しかなかった刑罰に、懲役刑が加わりました。他の藩も寛保2年(1742)に幕府から出された『公事方御定書』(寛保2年「事件・風俗」参照)にならって刑法を作っていましたが、この懲役刑は当時としては類のない新しい制度でした。
また、重賢は殖産興業にも積極的に取り組みます。養蚕を進め西陣の織物技術を農村にまで広めたり、蝋燭の原料となる櫨や、紙の原料となる楮(寛保元年「解説」参照)の植林にも力を注ぎました。しかし、これらの利益は生産者のものとはならず藩のものとなったので、農民や商人による騒動が起きることもありました。
さまざまな藩政改革の中で、最も成果があったのは年貢の増徴でした。まず検地を行い、豊作・不作にかかわらず一定の年貢を徴収するという定免法を採り入れたのです。これも農民たちの強い反発を招きましたが、藩の財政が立ち直るきっかけとなりました。
一方、宝暦4年(1754)には藩校(寛永18年「事件」参照)の時習館を開設し、農民や商人の子弟にも門戸を開放するなど人材の育成にも努めています。重賢の藩政改革は一部の反発を受けたものの、藩の財政は立ち直り、藩の体制を強固なものとしました。
この年、江戸で談義本(「解説」参照)という新しいスタイルの小説『当世下手談義』が出版されました。これは大坂の談義僧である静観房好阿が書いたものです。全5巻7編の話から成るこの本は、江戸町人の風俗を描いたもので、笑いを介して江戸の人々に教訓を与える内容となっています。
例えば、その頃の江戸でもてはやされていた心中物や姦通物の芝居を批判するために、歌舞伎に登場する工藤祐経の亡霊の口を借りて「忠臣孝子義婦烈女」の芝居を見せてくれと言わせるのです。まるで談義のように人々に語り掛けるような口調で、近年のぜいたくな葬式や、像の縁起を偽ったでたらめばかりの出開帳、豊後節(元文4年「出版・芸能」参照)の流行などが、次々と槍玉に挙げられていきました。
これまで、関西の浮世草子などを楽しんでいた江戸の人々にとって、この『当世下手談義』は江戸ことばを使い江戸町人の生活を取り上げた最初の作品だったため、江戸生まれの滑稽小説として歓迎されました。
多田南嶺の生まれた年ははっきりしませんが、18世紀前半を代表する著述家の1人と言えるでしょう。学者としても、小説・戯作の作者としても、その活躍は目覚ましいものでした。
南嶺という名は通称で、学者としては一般的に義俊と呼ばれました。また、どのような理由があったのか、南嶺の書いた浮世草子は八文字自笑(延享元年「人物」参照)の名で出版されていました。つまり、南嶺は自笑のゴーストライターだったのです。
多田家は古くから故実学を得意とする学者の家柄でした。そのため南嶺も若い頃から学問の道に励み、故実学を中心として神道学・国学なども取り入れて講義を行っていたようです。活動範囲は大変広く、京・大坂をはじめ江戸でも講義を開き、また奈良や名古屋にも門下生がいるほどでした。さらに大名家や高家に招かれることも珍しくなく、伊勢神宮からも講演に呼ばれるなどしており、一流の学者だったのです。特に、この南嶺を一躍有名にしたのは『旧事紀偽書明証考』でした。その頃の神道界や歴史学者の間でほとんど聖典視されていた『旧事紀』の間違いを、『古事記』『日本書紀』を根拠として証明したものです。この本は神道学の世界に新風を吹き込んだのでした。
このように学者として精力的な活動をしていた南嶺ですが、八文字屋の浮世草子も執筆するようになります。一説によると生活のためにゴーストライターになったとも言われますが、本当のところはわかりません。南嶺の作品だと思われる浮世草子は、南嶺と交際があった神沢杜口が執筆した『翁草』の記事などから見て、約30冊にも及ぶと言われます。それまでの八文字屋の浮世草子は、江島其磧(享保8年「人物」参照)によって書かれ人気を集めていました。そのあとを受けて南嶺は執筆にあたったのです。南嶺の実力は「其磧が筆法に劣らず、しかも当世の気を呑み込て書く故に、物によりては其磧をも圧り(上回った)」(『翁草』)と言われるものでした。
浮世草子というのは、当時の世相・風俗はもちろんのこと、芝居や遊里の最新事情にも通じていなければ書けないものでした。南嶺はどこでどう情報を集めていたのでしょう。学者としての南嶺からは想像できませんが、市井の人々にも講義を行っていた南嶺の日常は、あるいは遊里の世界や庶民の娯楽に近接していたのでしょうか。
南嶺は寛延3年9月12日に没しました。