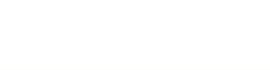

2月、土佐山内(松平)家隠居の玉仙院(寛保3年・宝暦8年「説明」参照)の年寄より、勤行用釣鐘を鋳造したい旨の申し出がありました。天英院の寄進した鐘は時の鐘として打つときのほかは撞かないので、法事などの折に撞く鐘が必要でした。祐海は、本堂の東に柱を4本建てて差し渡し、2尺5寸(75センチメートル)の鐘を鋳造して釣りたい旨を、寺社奉行の大岡越前守に願い出て許可を得ました。
2月19日、納所の忍貞が鋳物師の粉川(神田住、粉川市正藤原宗次)のところへ行き、3月10日までに釣鐘を造るよう申し付けました。3月6日に釣鐘ができ上がり、大八車に積んで人足2人掛かりで祐天寺へ運び、引き渡されました。
3月9日、釣鐘供養が行われました。四つ時(午前10時頃)過ぎに本堂より練り出し、惣衆が出勤しました。洒水は南蓮寺祐門が勤めました。讃鈸、四奉請、弥陀経、念仏回向が終わって、祐海が撞き初めに三下し、次に施主の玉仙院の代参である岩田が三下しました。鋳物師粉川が撞いてまた念仏回向をして供養は終了しました。その日は土佐山内家より年寄吉尾、そのほか30人余りの女中が参詣し、それらの人々へ正味五菜の饗応をしました。鋳物師粉川へは盛物2重、赤飯2重、酒2樽と祝儀金を遣わしました。
3月、祐海は大岡越前守へ召され、天英院のかねがねのお考えであったということで境内2、000坪拝領を仰せ付けられました。老中、寺社奉行にお礼回りをしました。
3月12日、竹姫より葵紋付き幕が寄進されました。
9月18日、文昭院殿33回忌につき、月光院は増上寺に仏参しました。祐海は増上寺で月光院をお迎えすることを希望し、許されました。
18日は快晴。祐海は七つ時(午前4時頃)駕籠で出て、増上寺に詰めました。四つ時(午前10時頃)月光院が到着しました。装束所の門前で増上寺住職、別当、役者たちとともに祐海も並んでお迎えしました。月光院は文昭院殿、有章院殿、清揚院殿、天英院の霊屋に参詣したのち、御殿へ入り休息されました。休息の間に祐海は御錠口まで呼び出され、「今日はそれには格別のこと。お逢いしたく思うができないのでことのほか残念に思う。このことをよく申せ」との御意であると年寄方より伝えられて、文庫の中から内々にと、銀5枚、巻物5巻を、方丈へは銀2枚、別当の4人、役者の4人へは銀3枚を御付台にて下されました。
その日のお供は若年寄の西尾隠岐守、寺社奉行の大岡越前守、留守居の内藤越前守、用人の高井長門らでした。
11月26日、鎮守宮を上棟しました。もともとこの地に熊野宮に付随して建てられていた稲荷宮に四谷天白稲荷のお札を納め、両社を四谷右山稲荷としました。そして、随身稲荷(享保3年「祐天上人」参照)とともに祀ったのでした。現在も祐天寺境内に祀られる、五社稲荷(随身、松黒、富山、天白、妙雲の5社)の前身です(寛延元年「祐天寺」参照)。
12月、寺社奉行月番の松平右近将監に、天英院御座の間の材料を使って天英院仏殿および書院などを建立することを願い、許されました。
増上寺内の弁才天は、貞享2年(1685)に霊玄が霊夢を受けて勧請したものです。宝珠院を別当とし宝珠院内に安置されていましたが、延享元年に堂宇を整えて増上寺内の芙蓉島へ移されました。その昔、天台宗の僧の円珍が唐へ渡るとき、海が荒れたため龍神に祈願したところ、海上に天女が現れて海が鎮まったという逸話があり、帰国後に円珍がその天女の姿を彫ったものが、この弁才天であると言われています。初めは鎌倉法華堂にありましたが、縁あって増上寺へ納められました。
青梅御嶽山にある御嶽神社は武州御嶽とも呼ばれ、崇神天皇または安閑天皇の代に創建されたと伝えられる、大変古い歴史を持つ神社です。火難・盗難除けの守護神として崇拝され、江戸時代においても幕府の帰依が篤く、江戸城の鎮守神ともなりました。2月から、護国寺においてこの御嶽蔵王権現が開帳されました。
米の価格がまた下落し、再び幕府がその対応に乗り出さざるをえなくなりました。9月、全国の米問屋に米の買い置きが命じられます。市場に米が出回らなくなれば、需要が増えて米の価格が上がると判断されたからです。この発令と同時に、御家人が札差を通じて借りた金は米価が上がるまで返さなくても良いというお触れも出されました。また翌月には、本来なら相対済し令(享保4年「事件・風俗」参照)により奉行所では取り上げないことになっていた金銀貸借に関する訴訟に対しても、米の買い置きのために金を借りたという件は、特別に奉行所でも取り上げることが布告されました。さらに12月には、米の買い置き令を顧みずにひそかに米を売買するような者を取り締まるため、江戸に米吟味所を設けました。
実学を好んだ吉宗は、天文・暦学にも特に力を入れていました。これらの学問により季節の移り変わりを知ることができるため、農民が農作業の予定を立てるなどの役にも立つと考えていたからです。渾天儀という天体の位置を観測する機械を作り、貞享暦に見る天体の動きと実際の天体の動きとの違いを発見した吉宗は、改暦の必要性を強く感じます。
そこで吉宗は、江戸で天文学を教えていた西川正休〔西川如見(享保9年「人物」参照)の子〕を吹上苑に召して、観測を行わせました。当時の幕府天文方であった渋川則休は未熟であったため、吉宗は則休の指導・補佐役として正休を抱えることにしたのです。
延享元年、吉宗が自ら考え出した、渾天儀よりも簡単に天体観測を行える簡天儀やほかの観測機械を、神田佐久間町(外神田付近)に移してここに天文台(当時は「司天台」と呼ぶ)を設けます。正休は延享4年(1747)に正式に天文方として登用され、則休とともに改暦の準備を進めていったのです。しかし、かつては改暦権を一手に握っていた京の陰陽頭土御門家(「解説」参照)との折衝がうまくいかず、やがて吉宗の薨去後に正休は失脚し、結局は何の改変も加えられない「宝暦暦」(宝暦4年「事件・風俗」参照)ができ上がるのでした。佐久間町の天文台は宝暦7年(1757)には取り払われ、のちに牛込に移されました。
将軍吉宗は寛保2年(1742)3月、評定所に元和元年(1615)以後の幕府法令の編集を命じました。老中の松平乗邑を主任に命じ、御定書掛の三奉行に編集させたのです。元和元年から寛保3年(1743)までの129年間に出された3、550通の法令を80部に整理・分類した成果は、延享元年に吉宗に提出されました。このときの書名は『御触書』でしたが、のちに撰された御触書と区別するために、『寛保集成』と呼ばれるようになります。
7月、市村座で累物の歌舞伎『開闢今川状』が初演されました。しかし、その内容は不明です。
慶安年間(1648~1651)京において、浄瑠璃本の版元八文字屋(元禄12年「解説」参照)を開いた八文字自笑は、本名を安藤氏と言います。八文字屋は代々「八文字屋八左衛門」の名を受け継ぎ、初めはごく普通の書店でしかありませんでした。しかし、元禄元年(1688)頃に2代目(あるいは3代目)として家業を継いだ自笑(雅号)により、文学史上にさん然と名を残すことになるのです。八文字屋は浄瑠璃本よりも絵入狂言本の出版に力を入れ、浄瑠璃本では老舗の書店に劣っていたものの、元禄年間後期では絵入狂言本の出版において目覚ましい発展を見せました。
すでにこの頃から江島其磧(享保8年「人物」参照)と関係があったようですが、其磧と八文字屋との因縁が生じるもととなった役者評判記『役者口三味線』(元禄12年「出版」参照)が刊行されたのは、元禄12年(1699)のことです。この本はそれまでの役者評判記と違い、携帯に便利なようにと書型を横本にし、絵をふんだんに取り入れた内容が当時の人々には新鮮で、大変もてはやされました。気を良くした自笑は其磧を促し、元禄14年(1701)に浮世草子『けいせい色三味線』(元禄14年「出版・芸能」参照)を刊行。またもや大変な人気を呼んで、自笑は営業拡張のために麩屋町通誓願寺下ル西側から東側へと店を移しました。
宝永年間(1704~1710)は、自笑にとってまさに人生最上のときでもあります。役者評判記の版元としての「八文字屋」は、当時のほかの版元から抜きん出た評判を勝ち取りました。自笑が採用した横本の書型は、浮世草子の刊行においてはコストの節減にもなり、かなりの利益を得ることもできたのです。やがて、評判記では宝永5年(1708)から、浮世草子では宝永6年(1709)から、それまで無署名で出版してきた書籍に「作者八文字自笑」との署名を入れるようになると、自笑の名は世に広く知られるようになり、好評と利益とを一身に受けることになっていきます。もともと其磧は、八文字屋を版元として無署名の気儘さのうちに、さまざまな趣向を凝らした書籍を発表していくことを楽しんでいたのですが、自分の作品への世間の評判がすべて自笑へと向かうのはあまり気持ちの良いことではありません。正徳4年(1714)にとうとう其磧は、突然ほかの版元から刊行した評判記の序文において、今までの八文字屋刊行の評判記や草子の類は、実は全部自分が書いたものなのだと暴露します。このときから自笑と其磧の確執が始まったのです。
しかし当時は、今まで全く知られていなかった其磧が突然、八文字屋本の作者を否定する主張を述べても、取り合う人はほとんどいませんでした。自笑は、1代で八文字屋を名立たる書店へと成長させただけの、個性の強さと才能とを持ち合わせていたのです。いわゆる「寝返った」其磧に対して、自笑は徹底的な反撃を見せました。毎年正月に刊行する評判記の序文で其磧の説を否定し、自作であると主張を押し通していきました。其磧に代わる代作者として多田南嶺(宝暦2年「人物」参照)を立て、この対決は5年にも及びました。しかし、これにより八文字屋の信用が落ちることもなく、其磧に加勢をして八文字屋の勢いをそごうとするほかの版元にうんざりした自笑と、世間の評判があまり変わらないことを悟った其磧は、結局は享保3年(1718)に和解します。こうして八文字屋は、浮世草子において出版界を制覇したのでした。
自笑没後、その家業は子孫へと受け継がれていきましたが、しだいに衰退し、文化8年(1811)に廃業したところを見ると、自笑の存在がいかに大きかったかがうかがえます。