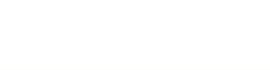

檀通上人は、増上寺の学頭職(学僧の最上位で、学僧を指導する立場)にありましたが、7月5日、館林(群馬県)善導寺に11世住職(『善導寺記』には開創から35世)として晋山(入山)しました。善導寺は関東十八檀林の1つで、歴史ある巨刹です。
祐天上人は、師檀通上人のもとで7年間学問を積み、この年18歳になっていました。学問はこれからが大事という年齢にあたり、師に随従して館林に行くか、増上寺に残って学問を続けるか、悩んだことでしょう。名刹と言っても地方の檀林に行くよりも、浄土宗総録所(僧階を授ける権限など持つ寺)である増上寺に残って勉強を続けたほうが、出世の近道でもあったのです。また、後に増上寺は、僧侶の数を制限するようになり、1度寺を出たらもう戻れない可能性もありました。
しかし、祐天上人は檀通上人に付き従い、館林善導寺に行ったのです。師僧のそばに仕えたいという、祐天上人の真心の表れだと思われます。
成田不動の伝説(慶安元年「伝説」参照)に対して、祐天上人がこもったのは、館林善導寺の不動堂だという言い伝えがあります。それによると、増上寺開山堂にこもり、白髪の老人より「不動尊に三七日(21日)の間断食して祈請せよ。そうすれば、頭が良くなる願いはかなえられるだろう」とお告げを受けた祐天は、ちょうど善導寺住職を拝命した檀通上人に随従して、館林善導寺に来ました。そして、ここの不動尊が行基菩薩の作と伝えられる霊験あらたかな尊像だと知り、参籠を決意したのです。満願の日、祐天の夢の中に身長1丈(約3メートル)余りの不動尊が現れました。この話の続きは、すでに慶安元年(1648)「伝説」でご紹介したことと同じです。
善導寺宝物の中には、「祐天上人直作木造不動尊」〔元禄7年(1694)正月2日奉納〕、「祐天上人吐血の衣並びに宝剣、および上人付嘱の諸品」などが伝えられていたそうです。(元禄7年「祐天上人」参照)
祐天上人は師匠檀通上人にかわいがられなかったという伝説があります。物覚えが悪かったため勘当されたというのです。明暦元年、檀通上人は館林善導寺の住職に決まり、旅立つ日が近付きました。けれども勘当されている祐天にはお供の声がかかりません。師匠についていきたい祐天は、ついに許可の出ないまま、増上寺を抜け出し、檀通上人の行列に見え隠れしてついていったというのです。この伝説の真相はわかりませんが、立派な上人も若い頃は苦労したとする、伝記作者の創作の可能性もあります。
9月、日光山について、条目が定められました。宮門跡(天皇家の皇子が住職となること)が山主となるのですが、後継者を決めるときには、まず朝廷より幼い皇子を申し降ろし、江州滋賀院に入って、学問修行していただきます。成長ののち関東に下向していただき、寛永寺隠室に居住して法統を伝えてのち日光山に移り、住職を継ぐということです。やめた前門跡も寛永寺隠室にとどまって、当住(現在の住職)を教え、頃合いを見て滋賀院に移る、となっています。この法度とともに、東照宮領1万石、大猷院(家光)領3、630石を寄進しました。それに対する税額は、100石につき金14両と定められましたが、門跡の領1、800石、学頭の領300石、日光奉行梶定良の600石は、非課税とされました。そのほか、神宝は毎年6月土用中に風に当てる、宮には祠官1人、僧侶6人、給仕1人、神人4人が毎日替わるがわる仕えよ、霊廟の守りは僧侶4人、神人4人などと、事細かに決められています。また、明暦元年11月、輪王寺号が天皇よりくだされました。
仮名草子。女性教訓書。北村季吟著。明暦元年刊行。中国同名書『列女伝』の翻訳で、孟母(孟子の母)あるいは舜(中国古代の聖王)の2人の妻のような賢女の逸話を例に、訓戒を詳しく説いています。「世の中やすらかに、民の戸をだやかにおさまりて、久しくあめのしたをたもち給ひて、舜のよはひ、もゝとせにはたとせあまり給へるころ、蒼梧といふところにてかくれおはしましき」というように、柔らかな感じを与える文章になっています。原典のくだくだしさをできるだけ省こうとしたのです。近世女性教訓書は本書に端を発するものと言うべきで、西鶴の『好色五人女』に間接的に影響を受けていると言われています。